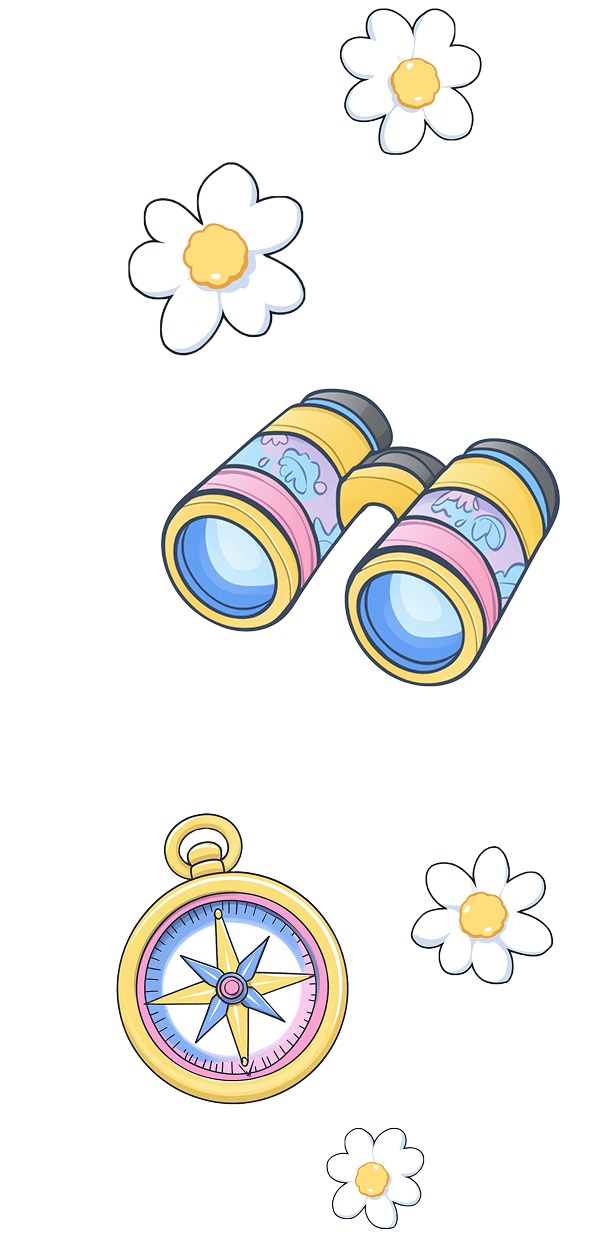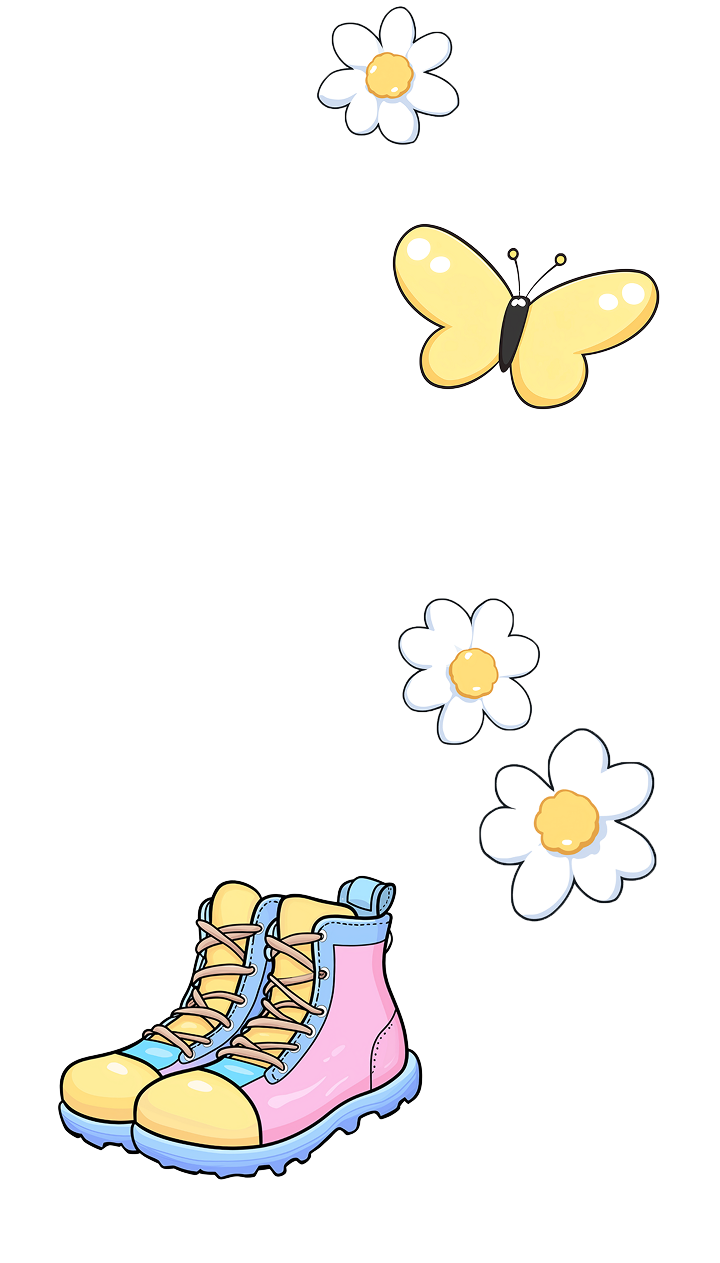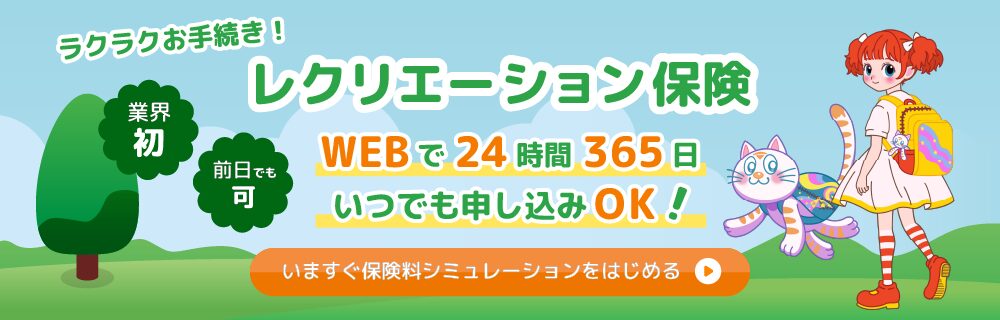高齢者介護におけるレクリエーションの目的

高齢者レクリエーションの目的
- 身体機能の維持や向上
- 認知機能の維持や向上
- 気分転換・リラックス
- コミュニケーションの促進
2025年には人口の約18%が75歳以上になる出典:厚生労働省「我が国の人口について」 5人に1人が高齢者となる未来はもうすぐ。高齢者一人一人の生活クオリティを守る必要があると考えられています。 レクリエーションは、高齢者の生活を整える目的もあるのです。 介護施設や病院では、高齢者へのケアとしていち早くレクリエーションが取り入れられています。 いろんなゲームやクイズを楽しんでいるだけで、認知や筋力低下の予防にもなるレクリエーション。 日々を気持ちよく過ごしてもらうためにも、レクリエーションは活用されています。新しい趣味や交流が生まれるきっかけにもおすすめです。
実際に介護現場で行われているレクリエーションは、大きく分けて4種類

| 4種類のレクリエーション | レクリエーションゲーム例 |
|---|---|
| 脳トレ系レクリエーション | 計算問題・漢字クイズ・思い出ゲーム・間違い探し・都道府県クイズ・手遊び体操 |
| 運動系レクリエーション | ラジオ体操・ボール体操・風船バレー・ボーリング・お手玉 |
| 創作系レクリエーション | 料理・絵・工作・折り紙・塗り絵 |
| リフレッシュ系レクリエーション | カラオケ・音楽鑑賞・動物との触れ合い・ハンドマッサージ・お花見・散歩 |
脳トレ系レクリエーション
脳トレ系のレクリエーションは、認知機能の維持や向上を目的に行われます。 頭を使ったり、指先を動かしたりする脳トレ系のレクリエーションゲーム。歌などに合わせてリズムを取って体を動かすのもおすすめです。 認知症は忘れっぽくなるだけでなく、自分自身もわからなくなってしまう可能性も。 脳の老化を遅らせ、元気に過ごしてもらうためにも、介護施設ではレクリエーションを取り入れています。運動系レクリエーション
気分をリフレッシュでき、リハビリ効果も期待できる運動系のレクリエーションは、介護施設で過ごす高齢者の方にも人気です。 ハードな運動ではなく、気軽に参加できるゲームや体操、ウォーキングなどを用意して、参加者を楽しませましょう。 体を動かすことで生活リズムが改善される可能性もあります。 室内でも行える簡単な体操は定期的に行うと筋力維持にも効果的です。介護士や介護スタッフは、怪我のないようサポートしてあげると良いでしょう。創作系レクリエーション
作る工程を考えたり、手先で細かい作業をしたりする創作系レクリエーションは、ストレス解消や認知症予防に最適です。 イラストを書いたり、小物を作ったりといろいろと楽しんでもらいましょう。 また、料理のスキルがアップすれば、高齢者の健康を支えることもできます。 創作系は男性が苦手とする場合もあるので、絵を書いたり、写真を撮ったりと男性が参加しやすいものを考えるのもおすすめです。リフレッシュ系レクリエーション
介護施設でも、高齢者の生活は、室内にいる時間が増えています。 外へのお出かけや、大きな声で歌うカラオケ大会など、気分転換におすすめなのがリフレッシュ系レクリエーションです。 季節ごとにお花見や夏祭り、クリスマス会などがあれば、季節が巡るのを楽しめますよね。介護士や介護スタッフも一緒に楽しめるイベントです。 介護施設全体のイベントとして考えても良いでしょう。高齢者に楽しんでもらうためのポイント

アイスブレイクを取り入れよう
アイスブレイクは、みんなの緊張を取り除くようなアクティビティのことです。 自己紹介をしてもらったり、好きなものを紹介するミニゲームを取り入れても良いでしょう。 すでに介護施設を利用していて、顔見知りが多ければ、お互いに話をする時間を設けても良いかもしれません。 Good&Newなど、良かったことや新しく知ったことを話してもらうのも楽しいですよ。レクリエーションゲームは簡単に説明しよう
レクリエーションゲームは、基本的には簡単なものばかりです。 しかし、介護施設で過ごす高齢者の中には、言葉でゲームの内容やルールを伝えても、よく分からないという方もいらっしゃいます。 介護士やスタッフで、実際に見本を見せたり、ジェスチャーを使ったりしてゲームを紹介するのがおすすめです。 「よく分からないな?」という方がいれば、もう一度ゆっくりと説明をしてあげましょう。サポート役も一緒に盛り上がろう
レクリエーションを実施するときは、サポート役の介護スタッフや介護士も一緒に盛り上がると、参加者も楽しみやすいです。 スタッフが実演し失敗してみたり、ゲームの最中に「せ〜の!」「もう一回!」などのかけ声を入れたりすれば、場も盛り上がりやすいでしょう。 みんなの様子を伺い、1人1人に良いところを伝えながらサポートするのもおすすめ。 負けたチームにも「頑張ってましたね!」や「今日一番の〇〇です!」など、いろんな声がけを考えてみてくださいね。みんなの輪を広げよう
レクリエーションは交流を深めるのにおすすめですが、高齢者にも、引っ込み思案の方やみんなと一緒に行動するのが苦手な方はいらっしゃいます。 参加したい気持ちを大切に、みんなの輪に入りやすいよう、介護士やスタッフはサポートしましょう。 レクリエーションを通して、新しい友達や趣味を見つけてもらえたら嬉しいですよね。レクリエーションを行う際に注意すべきこと

参加は自由!強要しない
高齢者の方はすでに自分の趣味・嗜好を持っている方がほとんど。好きでもないことをやって楽しいとは思えませんよね。 無理に参加するのではなく、自由に参加しやすい雰囲気を作りましょう。参加しないという選択を尊重し、好きなことを行って過ごしてもらえば、みんなが幸せで過ごせます。 いくつになっても、仲間といろんな遊びや交流ができることをレクリエーションを通して伝えたいですね。高齢者への言葉遣いに気を付けよう
高齢者に敬意を払って、日頃から敬語を使うよう心がけると良いでしょう。 介護施設で働いているとお世話をしているという認識になってしまいがち。 子供に向けるような言葉遣いになったり、上から目線の伝え方になったりするのは、NGです。 「疲れちゃったかな?」や「〜してあげるね」など、無意識に話してしまわないように、気をつけましょう。安全を確保する
高齢者は、思うように体を動かせなくなっている方も多いです。運動系のレクリエーションは、急に動いてバランスを崩してしまう可能性も。 レクリエーションを企画するときは、安全についてもしっかりと考えることをおすすめします。 例えば、車椅子の方がいれば、ロックしているか、運動するときに倒れないかなど注意が必要です。 他にも、片側麻痺がある方や耳が遠い方など、いろんな症状を持った方がいらっしゃいます。 倒れたり疎外感を感じたりしないよう、しっかりとサポートをしましょう。【高齢者・介護向け】おすすめレクリエーションゲーム7選

都道府県クイズ
高齢者の方は、今までにいろんな場所に行かれている人も多いです。思い出や記憶を頼りに都道府県のクイズに挑戦してもらいましょう。イントロクイズ
昭和の歌謡曲や演歌など、高齢者の方がよく聞いていた音楽をリサーチして、イントロクイズをするのも盛り上がります。 レクリエーションをきっかけに、大好きだった歌を思い出す方もいるかもしれません。みんなが好きな歌なら、一緒に歌ったり口ずさんだりするのもおすすめです。 介護施設でイントロゲームを行う場合は、イントロの部分が短いと難しいので、できるだけ長めに音楽を準備しましょう。 答えが出なくて難しい場合は、5択にしてヒントを出してあげると良いかもしれませんね。 リフレッシュと脳トレの効果が期待できます。新聞紙で文字探しゲーム
高齢者の方は朝に新聞紙を読む人も多いですよね。朝読んだ新聞を使って、文字探しをしてもらいましょう。ボール体操
ボール体操は、柔らかいボールを使って行います。膝や手で挟んで筋力を使ったり、ボールを回して体を動かす体操です。 椅子に座って簡単にできる体操で、介護や生活習慣病の予防にも効果があります。卓上カーリング
テーブルの真ん中にテープを貼ったり紙を置いたりして的を作ります。お手玉などを用意して、的の真ん中を狙ってもらいましょう。 もちろん相手の玉を弾き出してもOK。最後に中央に多く玉が残っていた方が勝ちです。 お手玉などがない場合は、段ボールを合わせカーリング用の玉を作ってみては? カーリングやボーリングのようなゲームは、身体機能の維持などにおすすめです。カラオケ大会
高齢者も好きなカラオケ大会。歌を歌うことは、声を出し、口を動かすので、嚥下が苦手な方のリハビリにもなります。 楽しい歌に合わせて手拍子を入れてもらうのもおすすめです。 みんなが楽しみながらいろんなレクリエーションを絡めても面白いでしょう。 懐かしいメロディーを聞くことで、脳の刺激にもなります。気持ちよく歌ってもらうことでリフレッシュにもなりますね。パステルアート
パステル画は、チョークのような顔料を粉にして、綿棒や指、消しゴムなどを使って絵を描きます。 水や筆を使わないので、比較的簡単にできるアートです。消しゴムである程度直せるのもポイント。 絵手紙などにも人気のパステルアート。外に出かけた思い出などを絵にしてもらうのも良いでしょう。 絵を描くことは、脳トレやリフレッシュに最適です。資格講座で学んで介護施設を盛り上げよう!

-

-
関連記事
レクリエーション・インストラクターとは?仕事内容と資格取得方法を紹介
レクリエーション・インストラクターの資格講座では、レクリエーションを企画実践することについて学びます。資格の取り方やどんな風に仕事をするのかについて詳しく見ていきましょう。今回は、レクリエーション・インストラクターについて紹介します。 ...
記事まとめ