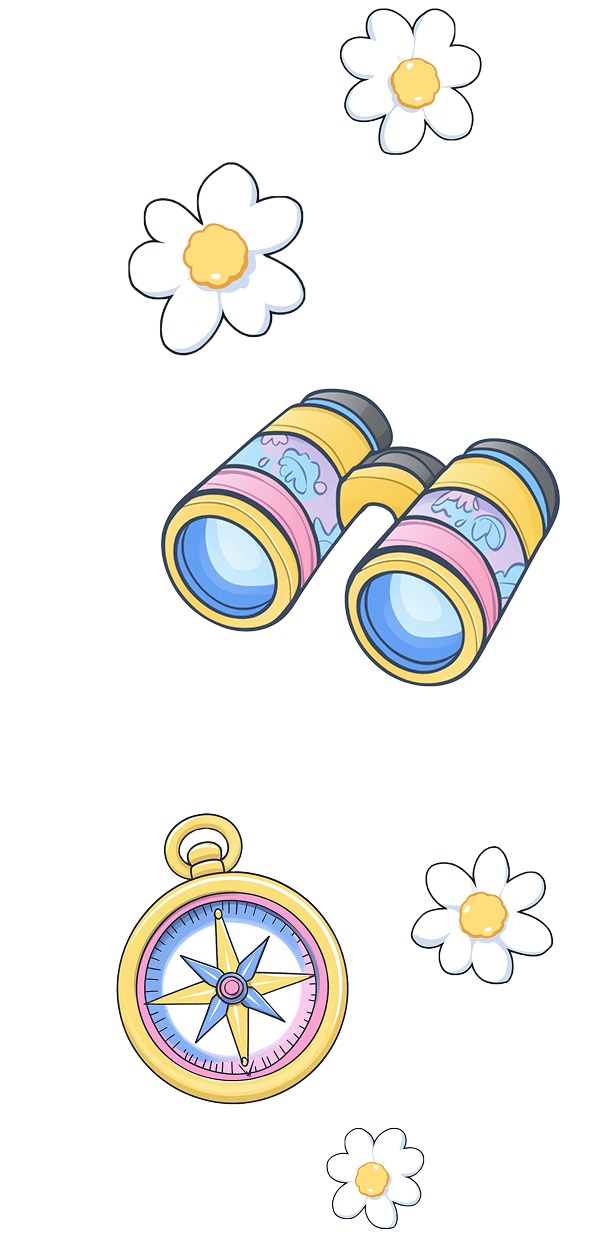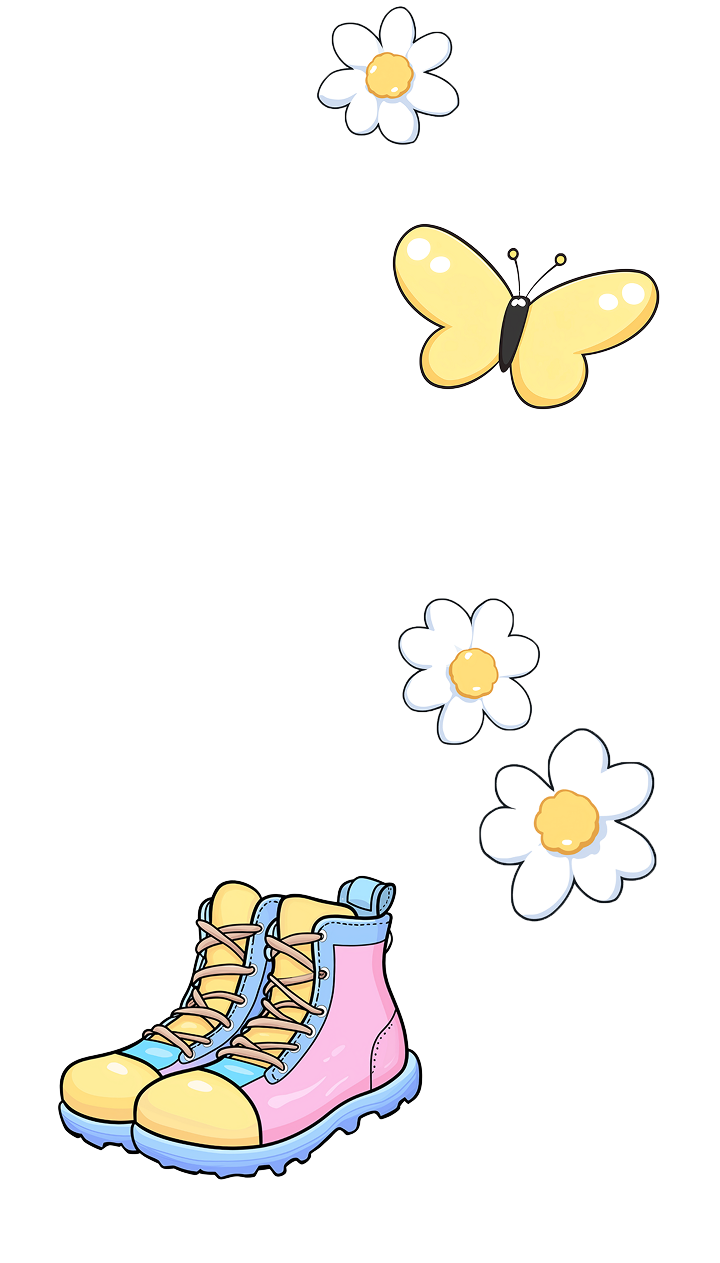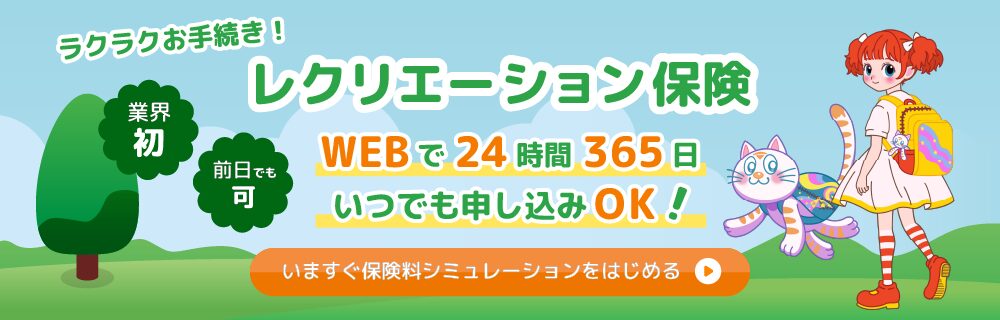スポーツやレジャーに備えられる「レジャー保険」とは

レジャー保険の補償内容

- 傷害死亡補償
- 傷害入院手術補償
- 個人賠償責任補償
- 携行品損害補償
- 救援者費用補償
傷害死亡補償
傷害死亡補償は、スポーツ・レジャー中の事故によるケガが原因で死亡した場合に保険金が支払われる補償です。 事故の発生から一定期間以内に死亡した場合に保険金が支払われます。 スポーツ中に重大事故が起こる可能性は十分にあり、最悪の場合死亡してしまうケースも考えられます。 万が一のことも考え、傷害死亡補償を受けられるレジャー保険への加入がおすすめです。傷害入院手術補償
傷害入院手術補償は、スポーツ・レジャー中の事故によるケガが原因で入院・手術をした場合に保険金が支払われる補償です。 事故の発生から一定期間内の入院・手術を対象に保険金が支払われます。 また、レジャー保険によっては退院後の通院を補償する「傷害通院補償」を備えている場合もあります。 通院治療もしっかりと補償したい場合は、傷害通院補償が備わっている商品・プランを検討しましょう。個人賠償責任補償
個人賠償責任補償は、第三者にケガを負わせてしまったり、他人の持ち物を壊してしまったりした場合に保険金が支払われる補償です。 スポーツ中の不慮の事故によって損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。 スポーツは想定外の事故が起こる可能性が高く、ケガを負わせてしまったり、持ち物を壊してしまったりするリスクは十分に考えられます。 普段からスキーやスノーボード、ゴルフなどのスポーツを楽しむ方にとって、個人賠償責任補償は必要性が高い補償のひとつです。携行品損害補償
携行品損害補償は、自身の携行品(持ち物)が破損・盗難の被害に遭った場合に保険金が支払われる補償です。 事故発生時点の携行品の価格または修理にかかる費用が補償されます。 スポーツ用品は高額なものも多く、破損・盗難による被害は大きな損失となります。 ゴルフであればゴルフクラブ、スキー・スノーボードであれば板やストックなど、道具にこだわりがある人ほど被害によるダメージは大きくなるでしょう。 レジャー保険であれば高額なスポーツ用品の損害も補償されるためおすすめです。救援者費用補償
救援者費用補償では、遭難した場合の捜索費や事故で入院した場合に家族が現地まで駆けつけるための費用が補償されます。 スキーやスノーボード、登山などで遭難した場合や旅行先で事故に遭って入院した場合などに保険金が支払われる補償です。 商品やプランによって補償される範囲が異なるため加入前によく確認しておきましょう。スポーツやレジャーに合ったプランを選択できる

レジャー保険の選び方

ポイント
- 補償内容に重複がないかよく確認する
- スポーツ・レジャーの頻度に合わせて契約期間を選ぶ
- 保険料と補償内容のバランスを取る
補償内容に重複がないかよく確認する
レジャー保険を契約する際、すでに加入している保険と補償内容が重複していないか確認しておきましょう。 すでに補償できている場合、レジャー保険に支払う保険料が無駄になってしまう可能性があるためです。 例えば、入院・手術に関する補償は医療保険でカバーできるケースがあります。 また、個人賠償責任補償は火災保険や自動車保険などに付帯されていることが多いです。 補償内容が重複した複数の保険に加入していると、どちらか一方からしか保険金・給付金を受け取れない可能性もあります。 まずは補償内容が重複していないか確認し、無駄のない保険プランを設計しましょう。スポーツ・レジャーの頻度に合わせて契約期間を選ぶ
レジャー保険は、商品やプランによって「1日単位」「1年単位」などの保険期間が設定されています。 保険期間は、スポーツやレジャーの頻度に合わせて選ぶことをおすすめします。 例えば年に1〜2回だけスポーツを楽しむような場合、1年単位のレジャー保険に加入する必要性は低いです。 スポーツをする日だけ補償される1日単位のレジャー保険を契約し、保険料の負担を安く抑えた方が良いでしょう。 一方で毎週のようにゴルフに行くような場合、1日単位のレジャー保険を毎回契約するのは負担が大きく、結果的に保険料も高額になります。 1年間補償が継続するタイプのレジャー保険がおすすめです。 ご自身のスポーツ・レジャーの頻度を踏まえ、自分に合った保険期間の商品・プランを選択しましょう。保険料と補償内容のバランスを取る
スポーツやレジャーでのリスクに備えるため、補償内容を手厚くしたい方も多いでしょう。 しかし補償内容が充実するほど保険料も高額になっていくため、保険料と補償内容のバランスを考えることも重要です。 万が一のリスクに対する補償はもちろん大事ですが、家計に負担をかけて日常生活が苦しくなってしまっては意味がありません。 補償内容をシンプルで過不足のないものにし、負担する保険料をなるべく抑える工夫をすることが大切です。 「とにかく補償を手厚くする」のではなく、保険料とのバランスを見ながら最適な補償内容を備えましょう。まとめ