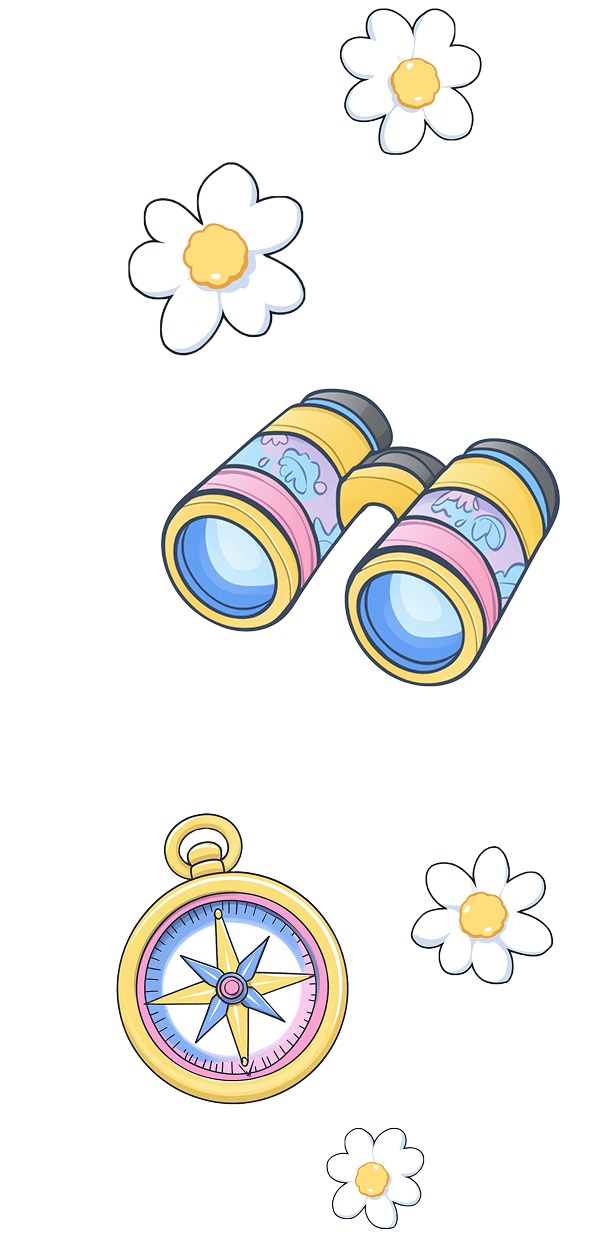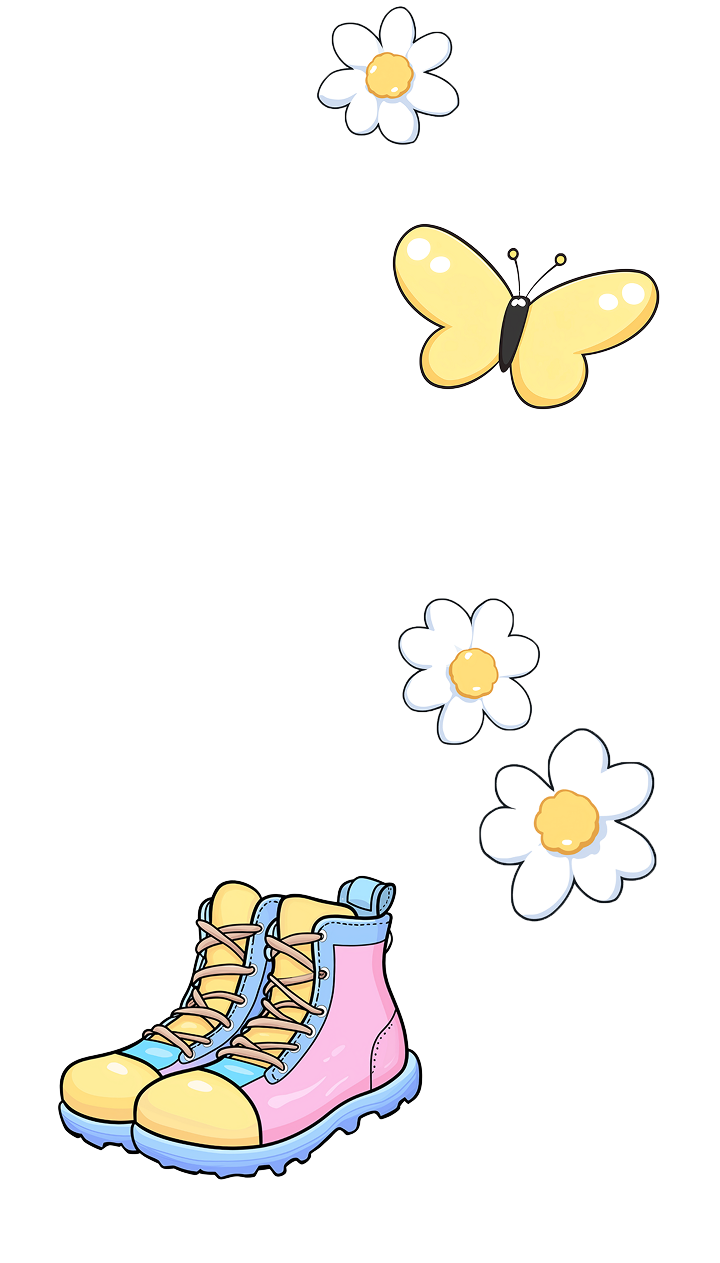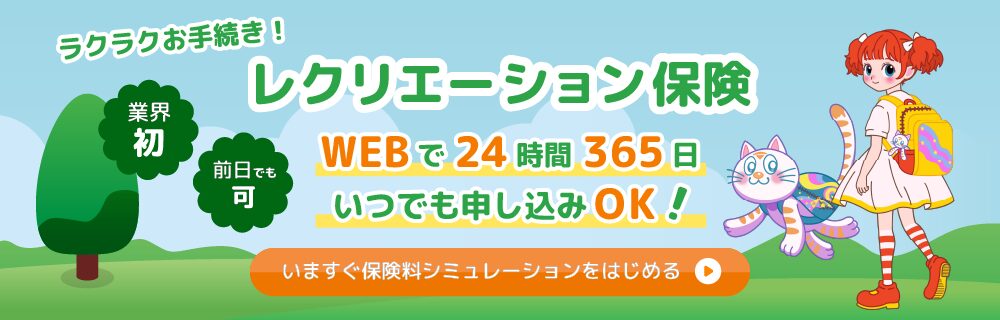学校行事とは?その目的や行われる理由
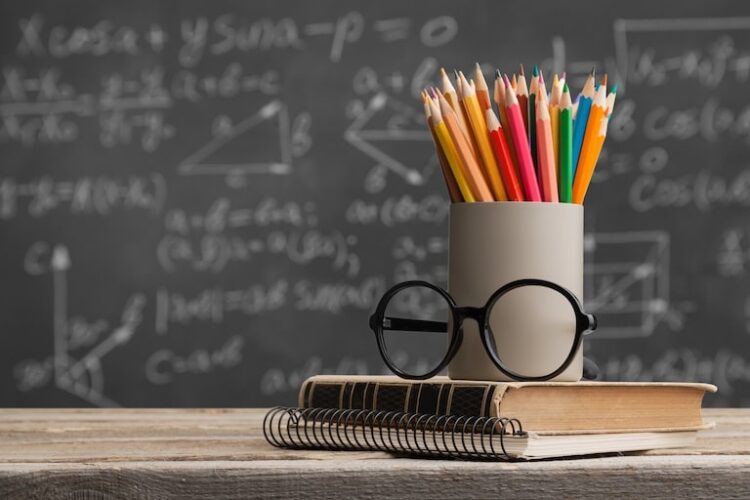
学校行事を通して,望ましい人間関係を形成し,集団への所属感や連帯感を深め,公共の精神を養い,協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。さまざまな学校行事を通して、より良い人間関係を築くこと、集団の一員として学級や学校の他の子ども・生徒と連帯して生活すること、自主性を育てることといった目的があります。
学校行事は5つの種類に分けられる
学校行事は、活動内容の目的やメリットに応じて、次の5つの種類に分けられます。| 行事の種類 | 学校行事の例 | 内容 |
|---|---|---|
| 儀式的行事 | 入学式、卒業式、始業式、終業式など | 学校生活の節目に、厳粛で清新な気分を味わい、 新生活をするきっかけとなる学校行事 |
| 文化的行事 | 文化祭、音楽祭(合唱祭)、学習発表会、展覧会など | ふだんの勉強や授業の成果を発表することで自己肯定感を高めたり、 文化・芸術に親しんだりする学校行事 |
| 健康安全・体育的行事 | 体育祭、運動会、競技会など | 心身の健全な発達や健康の保持・増進、 事故などから身を守るためのスキル、 集団行動におけるルールの体得、責任感や連帯感の育成、 体力向上などを目的とする学校行事 |
| 旅行・集団宿泊的行事 | 宿泊学習、修学旅行など | ふだんとは異なる生活環境で学んだり、 自然や文化に親しんだりして、 集団生活の送り方や社会のルールなどを体験する学校行事 |
| 勤労生産・奉仕的行事 | 学校周辺の清掃作業、美化運動など | ボランティア活動などの社会奉仕をすることで、 勤労の尊さや生産の喜びを体得するための学校行事 |
学校行事のメリットとは

学校行事のメリット①:人間関係の形成の仕方を学べる
集団生活では、さまざまな考え方に触れたり、子ども・生徒によって関心を持つことや好みが異なったり、ときには意見が食い違うこともあることを体験します。 お互いに理解し認め合ったうえで、それぞれの良さを生かした人間関係を作り上げていけるというメリットがあります。 人間関係が良好になれば、一人ひとりの能力や個性、資質をさらに伸ばしやすくなるというメリットもあります。学校行事のメリット②:集団や社会への参画につながる
子ども・生徒一人ひとりが、自分の属するクラスまたは学校生活をより良いものにするために、集団に積極的に参画し、多様な問題を自らの力で解決していけるスキルが得られるというメリットがあります。 学級や学校内で培ったそのスキルが、将来的に地域や社会に対する参画につながり、今後の社会を背負っていく力になることも目的としています。学校行事のメリット③:自己評価を高められる
子ども・生徒によって、得意なことと不得意なことがあり、それぞれの良さが発揮できる場面が異なります。 勉強の得意な子どもは授業参観で発表する、運動の得意な子どもは運動会や体育祭でその運動能力の高さを披露する、絵画や書写が得意な子どもは芸術祭などで制作物をみんなにみてもらう、音楽の好きな子どもは音楽祭や合唱祭などで活躍することができます。 それぞれの良いところを発揮できる学校行事を設けることで、一人ひとりの能力を認め合い、それが子どもの自己評価を高めることができるというメリットがあります。 また、学校行事を通して、現在または今後の自分の課題を発見し、改善したりより素晴らしいものに切磋琢磨できるというメリットも期待できます。 自己評価を高めることができれば、受験の際にも役立てられることが期待できます。運動会や宿泊学習などのメリット

主な学校行事1:運動会、体育祭のメリット
運動会や体育祭はほとんどの学校で行われている行事で、親も楽しみにしている学校行事のひとつでしょう。 メリットの前に、運動会と体育祭はどう違うのかを簡単にご説明すると、運動会は主に幼稚園や小学校で行われる行事で、先生が主体となって進められます。 一方、体育祭は中学校や高校で行われる学校行事で、教員ではなく生徒が主体となって行われます。 そして、運動会や体育祭には子どもや生徒の成長に欠かせない大きなメリットがあります。メリット①「勝利」に向けて全力を尽くす精神を育む
運動会や体育祭は、「クラス対抗」や「紅白対抗」といったように勝敗がはっきりとするものです。そのため、勝利に向けて一丸となって全力で取り組むことの大切さを学べるというメリットがあります。 また、勝敗が決まった後も勝敗に関わらず、互いの健闘をたたえ合うことの素晴らしさを学べるというメリットもあります。メリット②集団行動力を身に付けられる
運動会には、行進やパレード、団体競技といった集団行動が多くありますが、規律ある態度でみんなで同じ行動をすることで、集団における自分という自覚が持てるというメリットがあります。 また、毎日のように練習を繰り返すことで、クラスや学年、学校全体の集団行動能力が向上するメリットもあります。メリット③責任感や自己肯定感を育てられる
中学校や高校では生徒が主体となって体育祭が行われ、小学校では先生が主体となりますが、5・6年生などの高学年の子どもたちも係活動や委員会などで運動会の進行に携わります。 低学年の子どもたちを誘導したり助けたりすることで責任感が育ち、また、親や地域の人たちが見守る中で学校行事を進めていくことで自己肯定感も育つという注目すべきメリットもあります。主な学校行事2:宿泊学習のメリット
小学校や中学校で行われることの多い学校行事に宿泊学習があります。子どもたちと先生とでさまざまな経験を通して、自分と向き合い、人間関係の築き方を学んだり社会のマナーを身に付けられたりできるというメリットがあります。 また、子どもの頃の自然体験は心身の成長に効果があるといわれており、自然の中で活動することで、自然の仕組みや素晴らしさを肌で感じ、豊かな感情を育めるというメリットも期待できます。 さらには、家族以外の人と寝食など多くの時間を共にすることで、子ども同士の関りが深まりいじめ防止にも役立てられることも。 日常とは違う場所で自ら積極的に活動することで、また、自分の身の回りのことは自分ですることで、自己肯定感を高められるというメリットもあります。 一見、授業や学力の向上とは関係ないと思われがちな宿泊学習ですが、学校の授業では得られない体験が、子どもや生徒の成長に総合的にいい影響を与えます。主な学校行事3:修学旅行のメリット
中学校や高校での大きな学校行事のひとつに修学旅行があります。生徒にとっては楽しみな内容が多く、思い出深い学校行事になることが多いですが、教員にとっては生徒の安全を常に考えなければならないため、大変な学校行事でもあるでしょう。 修学旅行は、知識を広げることやきまりを守って集団生活を送れるようになること、社会の守るべきルールを身につけることなど、生徒の成長に必要な目的が定められています。 知識を広げるという目的のために、沖縄県や京都府といった歴史の勉強に役立つ地域を選ぶ学校が多いです。 また、学校ではなく一般の人も多い環境の中で、社会のきまりをきちんと守れるように、グループ分けして自主的に行動できるようにするねらいもあります。 さらに、最近は国内にとどまらず海外へ修学旅行に行く学校も増えており、国際的な文化についての知識も得られるメリットがあります。 ちなみに、「公益財団法人 日本修学旅行協会」の「2019 年度実施の海外教育旅行の実態とまとめ(中・高)」によると、海外修学旅行先として選ばれる国top3は、1位が台湾、2位がシンガポール、3位がマレーシアとなっています。 いずれの場所も日本からのアクセスが良いというメリットがあります。【参考:公益財団法人 日本修学旅行協会「2019 年度実施の海外教育旅行の実態とまとめ(中・高)」】
https://jstb.or.jp/files/libs/2100/202010051652103909.pdf
学校行事にはレクリエーション保険で万が一の保障を