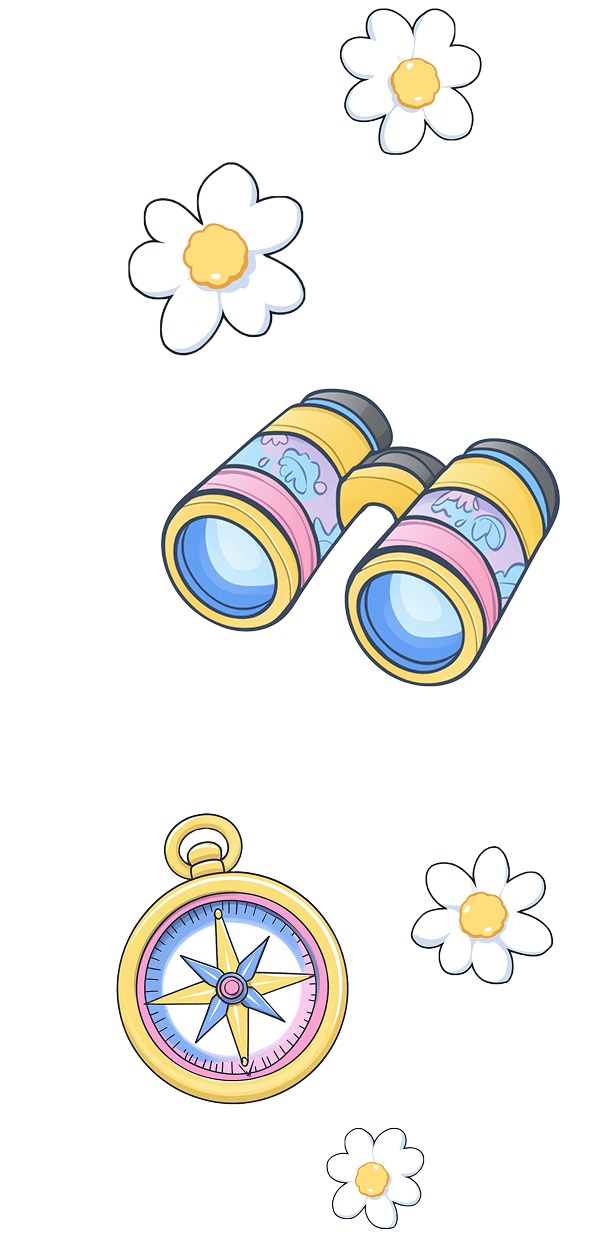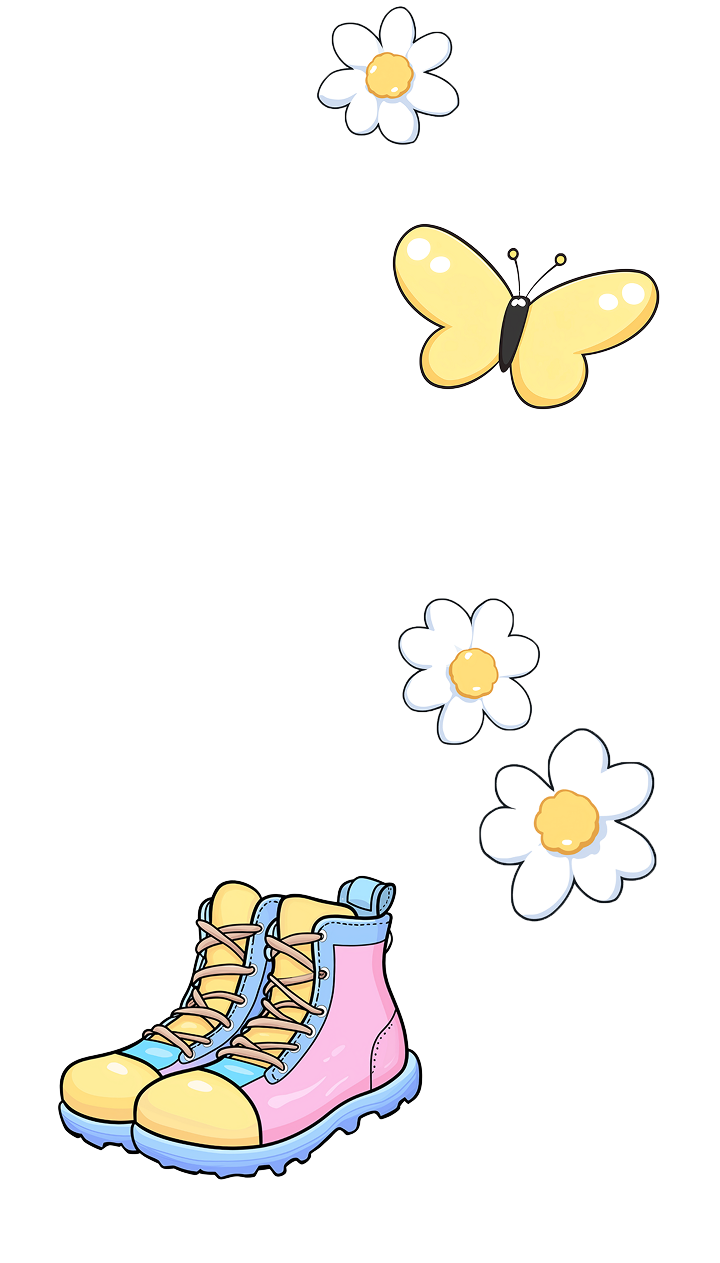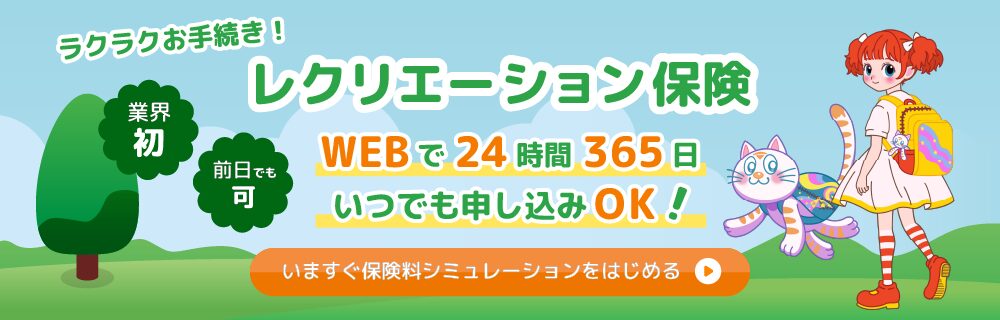レクリエーション保険はどんなケースが補償対象?

補償対象となるケガの例
- 施設内で子供が転倒、足を捻挫して通院した。
- サッカー中にボールが強くあたりけがをした。
- 食事を伴うイベントで集団食中毒がでた。
イベントの種類によって保険料が異なる点がポイント
レクリエーション保険はイベントの種類によって保険料が異なるのがポイントです。 例えば、いちご狩りや丘をハイキングするだけのイベントの保険料より、スポーツをするイベントの保険料のほうが高い料金で設定されています。 スポーツの種類によってはケガをするリスクが高くなるからです。 参考として、損保ジャパン日本興亜の「レクリエーション補償プラン」の保険料を見てみましょう。イベントごとに区分が分けられ、保険料が設定されています。| 区分 | レクリエーションの種類 | 保険料 |
|---|---|---|
| A | いちご狩り、いも掘、遠足(日帰り)、お花見、海水浴、ゲートボール、潮干狩り、ソフトボール大会、卓球、町内清掃、テニス、ドッ ジボール、なわとび、ハイキング、花火大会(市販程度の花火)、 バーベキュー、バドミントン、バレーボール、ボウリング、盆踊り、もちつき、ヨガ、ラジオ体操、料理教室 など | 30円 |
| B | ウィンドサーフィン、運動会、キャンプ(日帰り)、競歩、クレー射撃、サイクリング、魚釣り(船使用不可)、スケート、軟式野球(準硬式を含 む)、バスケットボール、ハンドボール、フィールドアスレチック、フェンシング、防災・避難訓練、マラソン、ボルダリング など | 150円 |
| C | カヌー競漕、空手、硬式野球、サーフィン、サッカー(フットサルを含む)、柔道、水上スキー、スキー、相撲、ホッケー、ラグビー、レスリング など | 300円 |
食中毒も補償の対象内!キャンプイベントに最適

食中毒を補償するには特約に加入する必要がある場合も
レクリエーション保険で食中毒を補償する際には、契約時に食中毒を補償する特約に加入する必要があることもあります。 基本補償として食中毒を補償する特約が付帯されている保険商品もありますが、特約をつけない限りは食中毒は対象外というものもあるのです。 たとえば、あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション保険では、「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約」があります。 この特約を付帯しておかないと、食中毒の患者が出たときに治療費を補償してもらえません。 レクリエーション保険に契約するときは、食中毒は基本補償の対象なのか、特約に加入する必要があるのか、契約条件をよく確認してください。 出典:あいおいニッセイ同和損保注意!宿泊を伴うイベント・行事はレクリエーション保険の対象外

宿泊を伴うイベントはNG
レクリエーション保険では、宿泊を含むイベント・行事は契約の対象外になります。キャンプやサッカー部の遠征など、宿泊をするようなイベントは要注意。 特にキャンプなどはカレー作りやバーベキューなどもあるため、レクリエーション保険で食中毒に備えようとお考えの方もいるかもしれませんが、宿泊を伴う場合は加入できませんので、ご注意ください。 デイキャンプ、日帰りの校外学習など、1日で行事が終わる場合には、レクリエーション保険はおすすめです。その他、保険金お支払いの対象外になるケース
その他にも、レクリエーション保険に加入していてもお支払いの対象外となるケースがあります。- 保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人がわざと事故を起こした、または大きな過失によって事故を起こした場合
- 被保険者による闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってケガ・事故が発生した場合
- 運転免許を持たずに車などを運転して、それによる事故でケガをした場合
- 地震、噴火もしくはこれらによる津波
まとめ:料理を行うイベント・行事の食中毒リスクにしっかり備えよう

食中毒も補償できるレクリエーション保険はこちら!
-

-
【あいおいニッセイ同和損保】イベント保険・レクリエーション保険一覧
行事・イベントを開催する際は、イベント保険やレクリエーション保険等に加入しておくと安心です。 この記事ではイベント保険の概要と、あいおいニッセイ同和損保が販売するイベント保険の内容をまとめています。 ...
続きを見る
監修者のコメント
記載の通り、行事参加者の食中毒はレクリエーション保険で補償できます。一方、学園祭に来場した不特定多数のお客様の食中毒等を補償するには、生産物賠償責任保険、施設賠償責任保険などを別途契約する必要がありますのでご注意ください。
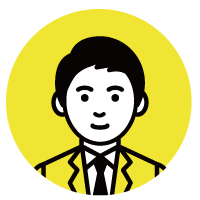
当記事の監修者:遠山直孝
- 保険コンプライアンス・オフィサー2級
- ファイナンシャルプランナー(AFP)
- 損保大学(法律・税務)※
国立大学卒業後、大手保険会社に27年勤務し、現在は損害保険代理店に所属。営業、企画部門での多彩な経験から、法律・税務を踏まえた実用的な保険の活用に精通しており、日々情報を発信しています。
※損保大学とは、損害保険の募集に関する知識・業務を向上させるために日本損害保険協会が立ち上げた制度。当監修者は「法律・税務」などの知識を深める専門コースを修めています。