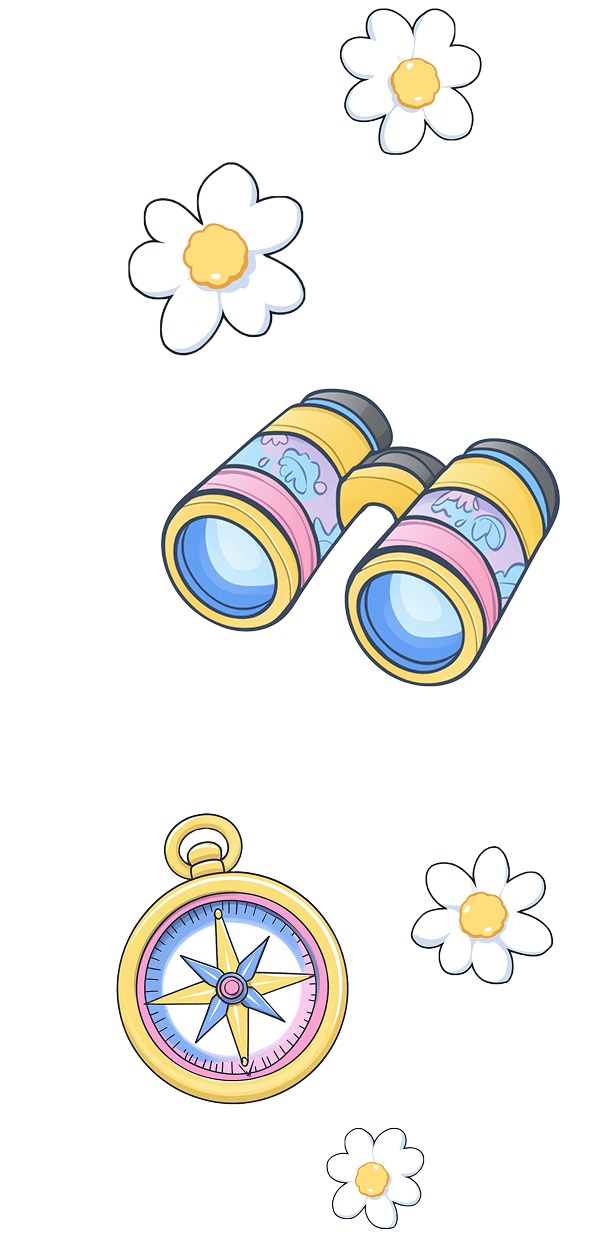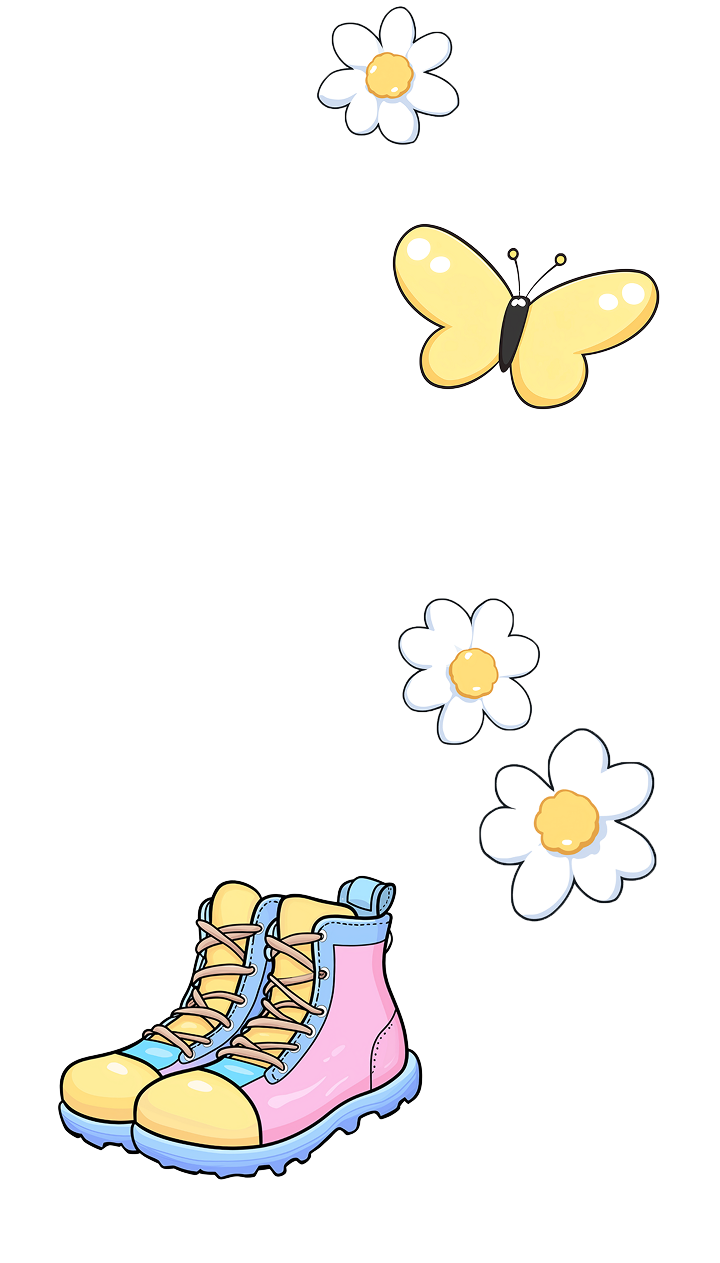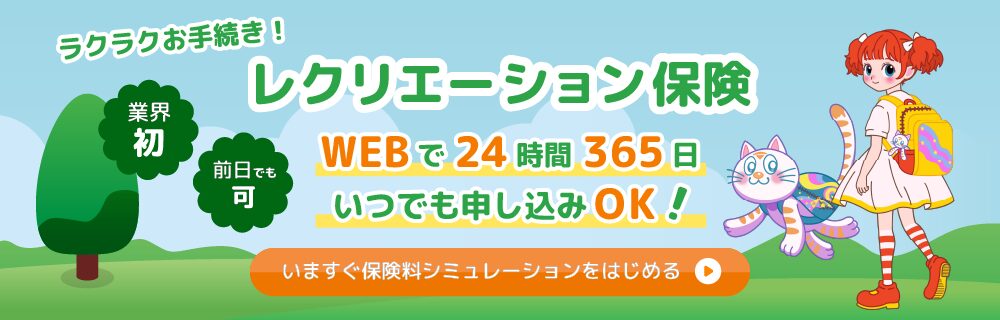「うちの子の部活、土日は休みになっちゃうのかな?」
「地域クラブに移行するって聞いたけど、費用はどれくらいかかるんだろう?」
そんな保護者の方々の疑問や不安に応えるのが、国(スポーツ庁)が示した「部活動の地域移行」の基本的な考え方(ガイドライン)です。このガイドラインは、子どもたちの活動や先生の働き方に関わる、とても大切な変化なんです。
この記事では、部活動の地域移行について、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 「いつから」「何が」変わるの?
- 保護者や生徒への主な影響
- 費用や万が一の事故の責任Q&A
この記事を読めば、令和5年度から令和7年度にかけて進められる改革の全体像と、ガイドラインで示された内容について、ご家庭で知っておきたいことが分かります。
まずは最新の情報を知って、これからの変化に備えましょう。
部活動の地域移行とは?スポーツ庁ガイドラインの概要

学校主体だった部活動を、地域のクラブ活動へ移す、部活動の地域移行の動きが本格化しています。
この地域移行の背景にある国のガイドラインや、ガイドラインが示す目的について、詳しく見ていきましょう。
なぜ今、部活動の「地域移行」が必要なのか?
部活動の「地域移行」が求められる背景には、二つの大きな社会課題があります。
一つは、教員の長時間労働を改善する「働き方改革」です。これまで部活動の顧問が、教員の大きな負担となっていたためです。
もう一つは、深刻な「少子化」の問題です。生徒数の減少によって、学校単独では部活動の維持が難しくなっているのです。
また、国のガイドラインが示す地域移行には以下のようなねらいもあります。
- 地域全体で部活動の場を確保し、子どもたちの多様なニーズに応える
- 地域の専門的な指導者を活用し、部活動の指導の質を高める
こうしたガイドラインに基づくねらいのもと、地域移行が進められています。
※参照 運動部活動の地域移行について | スポーツ庁
https://www.mext.go.jp/content/20220727-mxt_kyoiku02-000023590_2-1.pdf
スポーツ庁・文化庁が示す「総合的なガイドライン」とは
国は、部活動の地域移行改革について、具体的な方向性を示すガイドラインを策定しています。
令和4年12月に、スポーツ庁と文化庁が「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、従来の指針を統合・改定した最新のもので、部活動の地域移行における最も重要な指針となります。
「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる」という理念を掲げています。
学校と地域が協力し合い、持続可能で多様な活動環境を整えることを目指しているのです。
※参照 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の 在り方等に関する総合的なガイドライン | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/pdf/93813101_02.pdf
部活動の地域移行はいつから?最新の推進スケジュール

部活動の地域移行は、大きく2つの段階に分けて進められます。ここでは、令和5年度から始まる具体的な推進スケジュールを解説します。
ステップ1:改革推進期間(令和5年度~令和7年度)
国が定める部活動の地域移行は、国のガイドラインに基づき、段階的に進められます。
最初のステップとして、令和5年度(2023年度)から令和7年度(2025年度)までの3年間が、ガイドラインで「改革推進期間」とされています。
この期間の主な目的は、教員の負担が大きかった土日などの「休日」の部活動から、地域クラブへの移行を進めるためです。
ガイドラインでは、全国一律の期限を設けているわけではありません。各市町村が、指導者の確保や場所の整備といった受け皿の準備状況に応じて、できるだけ早い実現を目指す方針がガイドラインで示されています。
そのため、令和7年度は改革の「完了期限」ではなく、あくまで部活動の地域移行に向けた環境整備を着実に進めるための、大切な「節目」とガイドラインでは位置付けられています。
ステップ2:改革の本格実施(令和8年度以降)
「改革推進期間」が終わる令和8年度(2026年度)以降は、ガイドラインに沿って部活動の地域移行を本格的に実施し、定着させる段階へと入ります。
まずは休日の部活動移行で得られた成果や課題を評価し、さらなる改革につなげていく計画です。
この段階での焦点は、これまで学校が主体だった「平日」の部活動のあり方です。
スポーツ庁や文化庁は、ガイドラインの改革推進期間中から平日の活動の地域移行についても検討を進めており、令和8年度以降はこれを本格化させる方針をガイドラインで示しています。
有識者による会議で議論が進められており、休日と平日をあわせた活動を地域で一体的に支える、持続可能な体制づくりが目指されています。
地域移行で部活動はこう変わる!4つの主要な変更点

部活動の地域移行は、活動の運営主体や指導者が学校から地域へと大きく変わる改革です。
ここでは、国のガイドラインに基づき、部活動と地域移行に関するガイドラインが示す主な4つの変更点を解説します。
1.活動の主体:「学校」から「地域クラブ活動」へ
これまで学校が担ってきた部活動の運営は、ガイドラインに基づき、将来的に地域が主体となる「地域クラブ活動」へと地域移行していきます。
これは、教員の負担軽減だけでなく、少子化が進む中でも子どもたちが多様な活動を続けられる環境を作るためです。
運営の「受け皿」は地域によって異なり、主に以下のような形が作られつつあります。
- NPO法人が中心となるケース(長崎県長与町など)
- 民間事業者の専門ノウハウを活用するケース(沖縄県うるま市など)
- 新たに一般社団法人を設立するケース(千葉県柏市など)
- 既存の総合型地域スポーツクラブが担うケース(愛知県半田市など)
このように、地域の実情や資源に合わせた、柔軟な運営体制が作られ始めているのです。
※参照
https://www.mext.go.jp/sports/content/20250901-spt_oripara-000028260_01.pdf
2.指導者:「教員」から「地域の指導者」へ
活動の主体が変わることに伴い、指導者も学校の教員から「地域の指導者」が中心となっていきます。
各自治体では「人材バンク」などを整備し、指導資格を持つ地域住民や退職教員、大学生などの発掘を進めています。
気になる指導者への報酬(給料)は、ガイドラインによると主に以下の2つから支払われます。
- 参加する家庭が支払う会費(受益者負担)
- 国や自治体からの補助金
沖縄県うるま市のように、「企業版ふるさと納税」を財源に活用するユニークな例も出てきました。
もちろん、希望する教員が学校の仕事とは別に、報酬を得て地域の指導者として活動する「兼職兼業」の仕組みも認められています。
3.活動日時:「土日の部活動」の考え方
「土日の部活動が廃止される」と心配する声も聞かれますが、これは正確ではありません。
活動自体がなくなるのではなく、土日の部活動の運営主体が、学校から地域クラブへと移っていく、というのが国のガイドラインに基づく基本的な方針です。
国はまず、令和7年度(2025年度)までを「改革推進期間」と定め、休日(土日・祝日)の移行から着実に進めるよう呼びかけています。
これは、教員の負担軽減という目的を達成するために、休日の指導から見直すことが最も効果的だからです。
当面は「平日は学校の部活動、休日は地域クラブ」という形になる地域も多いかもしれません。
その場合、生徒が混乱しないよう、学校の顧問と地域の指導者がしっかり連携していくことが大切になります。
4.大会への参加:地域クラブも中体連・高体連の大会へ
部活動が地域移行し、地域クラブで活動する場合、公式大会に参加できるかどうかは大きな関心事です。
この点は、中学生と高校生で状況が大きく異なります。
中学生と高校生の大会参加の扱いは、以下の表のようになっています。
| 対象 | 主催団体 | 地域クラブの参加 |
|---|---|---|
| 中学生 | 中体連 | 〇 (令和5年度から条件付きで参加可能) |
| 高校生 | 高体連 | × (現時点では公式に認められていない) |
このように、中学生は地域クラブとして全国大会を目指す道が開かれましたが、高校生はまだ学校単位での参加が原則です。
中学で地域クラブに所属した生徒が、高校では大会に出るために学校の部活動に入り直す必要がある、という「ねじれ」が今後の課題と言えるでしょう。
【事例】すでに取り組んでいる自治体のガイドライン

全国の自治体は、教員の負担減や少子化対応のため、地域移行のガイドライン作成を進めています。
ここでは、東京都、茨城県・長野県の具体的な取り組み事例を見ていきます。
東京都の取り組み事例
東京都の改革は、都の「教員の働き方改革」という目的と、各区市町村の実情との間で進められています。
例えば、調布市の事例では外部指導者を活用するなど、「運営体制」の構築が進められています。
一方、墨田区の事例では運動が苦手な生徒向けのクラブを設けるなど、「生徒のニーズ」を優先する特徴が見られます。
同じ都内でも、自治体によって優先順位が異なっていることが分かります。
※参照 学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン | 東京都
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/bukatsu_guideline
茨城県取り組み事例
茨城県は、多様な運営モデルと財源モデルの「実験場」となっています。
例えば「NPO法人つくばフットボールクラブ」の事例では、学校を拠点としてクラブが設立され、NPO法人が指導者を派遣し、市内全域の中学生を広域から募集しています。
費用負担は受益者負担が原則ですが、経済的に困窮する家庭への支援も求められています。このように、財政力や考え方によって様々な選択肢が試されています。
※参照 茨城県地域クラブ活動ガイドライン
https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/wp-content/uploads/2023/02/01guideline.pdf
長野県佐久市の取り組み事例
長野県佐久市周辺は、他とは事情が異なります。
主な動機は、少子化による「部活動の存続危機」への対応であり、地域移行の背景となっています。
生徒数減少でチームが組めず活動継続が困難な点に加え、教員の負担軽減(働き方改革)も喫緊の課題となっています。
佐久市では、総合型スポーツクラブや民間事業者など「多様な主体」が運営を担うことを想定しています。まずは「剣道」などで先行的に地域移行のモデルケースを実施し、課題を検証しながら進めています。
地域の存続をかけた取り組みとなっているのです。
※参照
https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/sports/bukatudou/tiikiikou.files/saisyuuhousinn.pd f
保護者・生徒が知りたい「部活動の地域移行」Q&A

ここでは部活動の地域移行と、関連するガイドラインについて、特に気になる疑問をQ&A形式で解説します。
Q1.部活が地域移行した場合、ケガや事故の責任はどうなる?
活動の主体が、学校から地域クラブの運営団体に変わるためです。万が一の事故の責任は、学校ではなく、そのクラブが負うことになります。
学校の保険(災害共済給付)は使えません。
そのため、クラブ側で「スポーツ安全保険」など、賠償責任もカバーする保険へ加入しておくことが重要です。
Q2.地域クラブになったら、費用(月謝)はかかる?
はい、会費や月謝といった費用が発生する可能性が高いです。これまでの学校部活動と違い、「受益者負担」が基本となるためです。
会費は、主に以下のような費用に使われます。
- 指導者への謝礼(人件費)
- 運営管理費
- スポーツ安全保険などの保険料
ただし、経済的な理由で活動を諦めることがないよう、自治体による支援策も検討されています。
Q3.外部コーチ(指導者)の給料や謝礼はどこから出るの?
指導者への謝礼は、主に以下の3つの財源から賄われる想定です。
- 参加者が支払う「会費」
- 市区町村など「自治体からの補助金」
- スポーツ振興くじ(toto)など「国からの助成金」
地域の実情に合わせて、これらの財源を組み合わせて確保していくことになります。
Q4.ガイドラインを守らない学校や地域はどうなる?
国が示すガイドラインは、あくまで「指針」です。
法的な拘束力はないため、守らなくても直接的な罰則はありません。
ただし、競技団体が主催する大会の参加資格に、「ガイドラインの遵守」が条件として加えられる可能性があります。
これが、実質的にガイドラインを守る動機付けになると期待されています。
Q5.地域の受け皿(クラブ)がない場合はどうなる?
部活動の地域移行において、受け皿となるクラブや指導者の不足は、特に地方で大きな課題となっています。
この問題は地域差が大きいため、各自治体が中心となって環境整備を進める方針です。
その中核として、自治体が設置する『協議会』が調整役を担います。
地域の団体と連携し、指導者確保や学校施設の利用調整などを行うものです。
地域クラブ運営の「万が一」に備えるレクリエーション保険という選択肢

部活動が地域移行すると、運営の責任は学校から地域クラブ(主催者)に移ります。活動中のケガや施設の破損といった「万が一」のリスクに、主催者が直接備えなくてはなりません。
そこで知っておきたいのが、「みんレク」のような手軽なレクリエーション保険です。クラブ運営者にとって、以下のようなメリットがあります。
- 開催前日23時59分までネット申込OK
- 1人1日あたり数十円からの手頃な保険料
- 主催者を守る「賠償責任保険」も追加可能
- ケガや熱中症に加え、自宅との往復も補償
こうした保険を活用することで、運営者も参加者も安心して活動に集中できる環境を整えることができます。
まとめ

この記事では、学校の部活動が地域のクラブ活動に変わっていく「部活動の地域移行」について、国のルール(ガイドライン)をもとに解説しました。令和5年度から7年度にかけて、今まさに全国で部活動の地域移行が進められています。
この変化は、先生方の負担を減らし、子どもたちがスポーツや文化活動を続けやすくするためのものです。一方で、会費がどうなるか、指導者をどう探すか、万が一のケガの責任は誰が持つかなど、地域で考えるべき課題もあります。
部活動がどう変わっていくかは、住んでいる地域によって大きく異なります。まずは、お住まいの市や町が公開している、部活動の地域移行に関する最新情報をぜひ調べてみてください。
この変化を知ることが、安心して準備するための一番大切なステップになるでしょう。