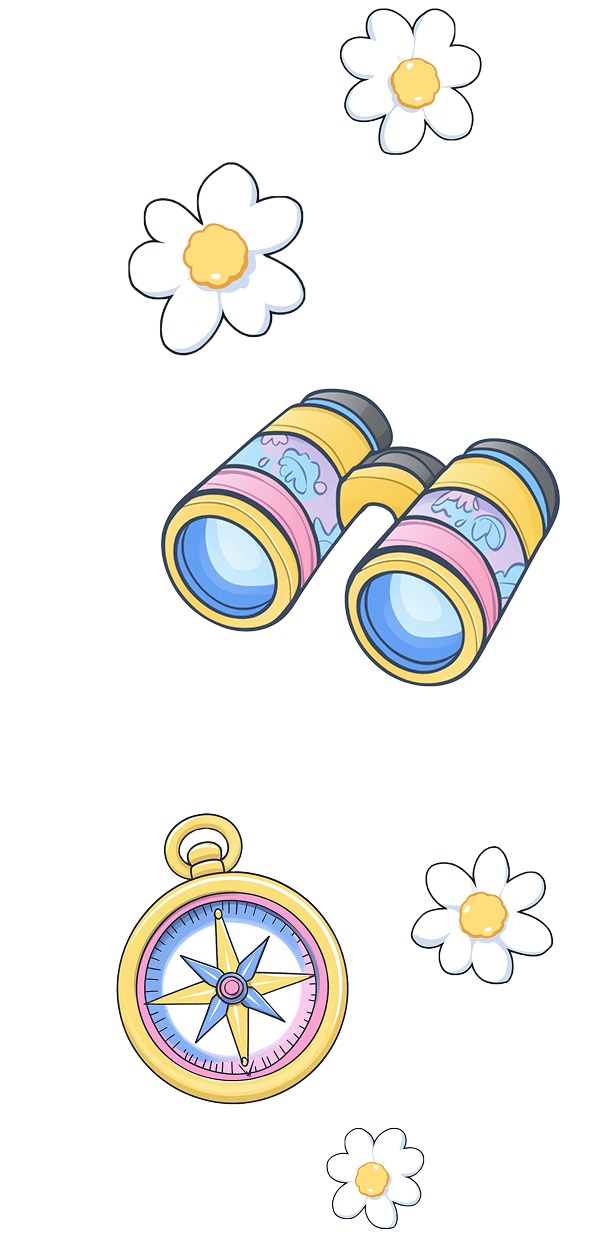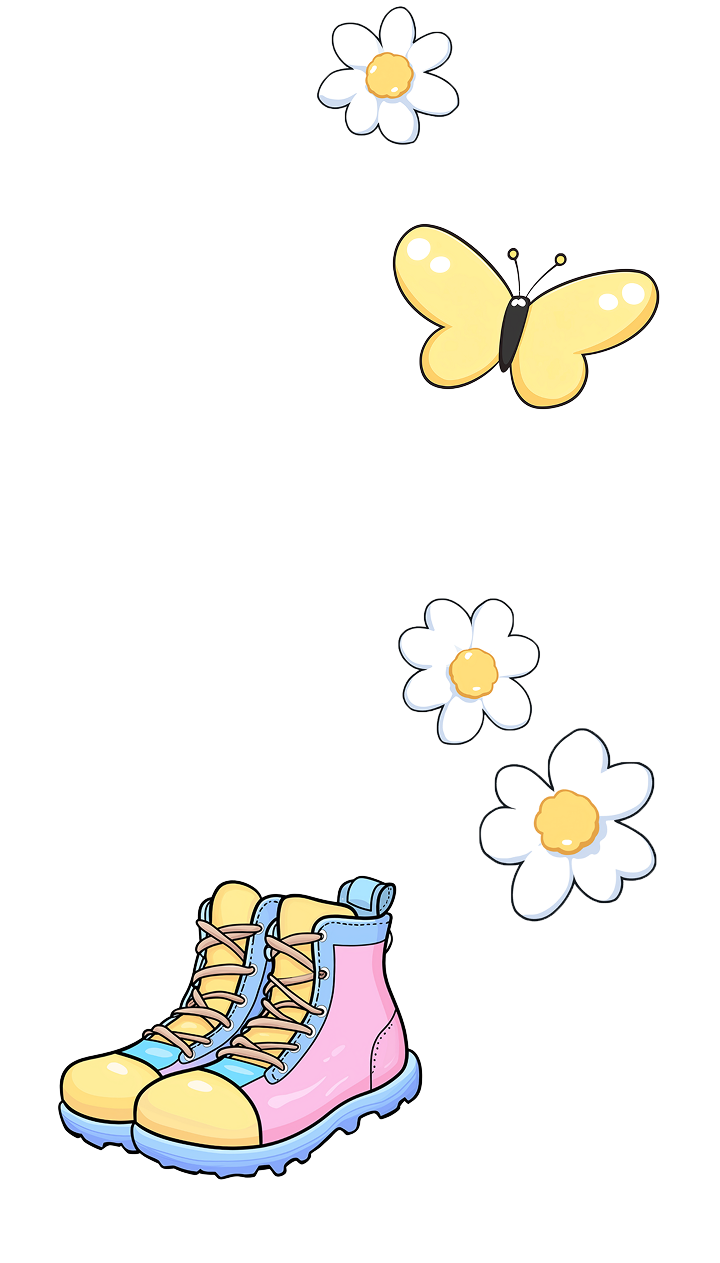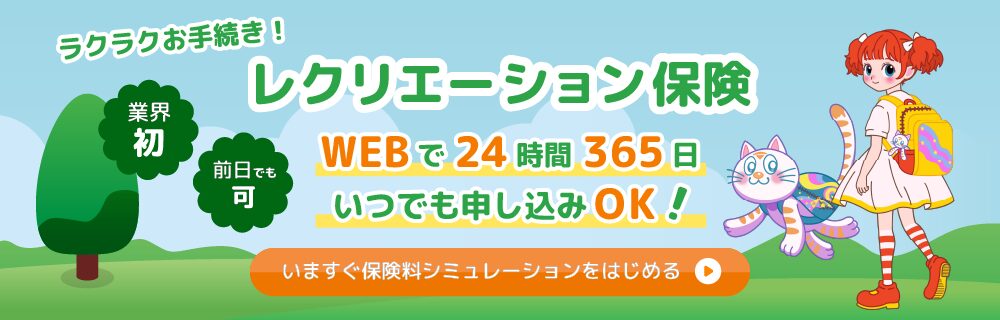スポーツ活動中の思わぬケガ。
そんな時に頼りになるのがスポーツ保険です。
スポーツ保険の請求手続きは、事故発生から保険金を受け取るまで複数のステップがあります。
「どんな流れで申請すればいいの?」「必要な書類は?」と疑問をお持ちの方も多いはず。
この記事では、スポーツ保険の保険金請求の基本的な流れや、スポーツ安全保険特有の事故通知方法から書類準備、東京海上日動への提出、そして保険金支払いまでの手続きを分かりやすく解説します。
特に団体活動中のケガに対する医療費請求の流れを知って、万が一の際にスムーズに保険金を受け取りましょう。
スポーツ保険の保険金請求の一般的な流れ

スポーツ活動中に事故やケガが発生し、スポーツ保険を活用して保険金を請求する際には、一定の手順を踏む必要があります。
以下はスポーツ保険の保険金請求の一般的な流れです。
- 事故発生時の対応
- 保険会社への事故通知
- 請求書類の準備
- 審査と支払い
スムーズに保険金を受け取るためには、正しい流れに沿って請求手続きを進めることが重要です。
ここでは、スポーツ保険の請求プロセスの基本的な流れを解説します。
1. 事故発生時の対応
スポーツ保険の請求プロセスは、事故やケガが発生した瞬間から始まります。
まず最優先すべきは適切な医療処置を受けることです。
その上で、ケガの状況をしっかり記録しておきましょう。
- ケガをした日時、場所、状況を詳細に記録する
- 可能であれば現場の写真を撮影しておく
- 目撃者がいる場合は連絡先を控えておく
- 医療機関での診断内容、傷病名を確認する
- 治療に関する領収書は必ず保管する
事故発生から保険金請求までのタイミングも非常に大切なポイントです。
保険金請求権には3年の時効があるため、できるだけ早く手続きを始めることをおすすめします。
2. 保険会社への事故通知
ケガの治療を始めたら、速やかに保険会社へ事故通知を行いましょう。
この手続きは保険金請求の第一歩となるもの。
以下の情報を準備しておくと、事故通知の手続きをスムーズに行うことができます。
- 団体名と団体代表者の氏名、連絡先
- ケガをした本人の住所、氏名、年齢、電話番号
- 加入依頼番号や加入手続日
- 事故の日時、場所、詳細状況
- 傷害の内容や入院の有無
事故通知が遅れると、保険金が支払われないことや減額される可能性があるため注意が必要です。
ただし、やむを得ない事情で通知が遅れた場合については、事実関係が確認できれば支払いの対象となることもあります。
3. 請求書類の準備
事故通知後、保険会社からスポーツ保険の被保険者(ケガをした人)宛てに保険金請求に必要な書類一式が送付されます。
主な必要書類は以下の通りとなっています。
- 保険金請求書(必要事項を記入)
- 医療機関の領収書(原本またはコピー)
- 診察券のコピー(場合により)
- 入通院申告書
- 同意書(場合により)
知っておきたいのは、入通院保険金請求額の合計が30万円以下の場合、保険会社から特別な求めがない限り、原則として医師の診断書の提出は不要という点。
これにより余計な費用負担を抑えることができるでしょう。
4. 審査と支払い
すべての書類が揃い、保険会社に提出されると、内容の審査が行われます。
この審査では、提出された書類をもとに事故の状況やケガとの因果関係、保険適用の可否などが確認されるのが一般的です。
審査に問題がなければ、指定した口座に保険金が振り込まれる流れです。
スポーツ安全保険の場合、入院は1日あたり4,000円、通院は1日あたり1,500円など、加入区分によって支払金額が決まっています。
また、審査から支払いまでの期間はケースによって異なりますが、書類に不備がなければ比較的早く進むことがほとんどです。
もし手続きに関して不明な点があれば、担当の保険会社窓口に問い合わせてみましょう。
スポーツ安全保険の請求の流れを紹介

ここまでスポーツ保険の請求の一般的な流れを解説してきましたが、スポーツ保険といえば「スポーツ安全保険」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
スポーツ安全保険は公益財団法人スポーツ安全協会が運営する保険制度で、多くのスポーツ団体や学校の部活動でも活用されています。
スポーツ安全保険は、一般的な保険請求の基本ステップを踏まえながらも、それ特有の請求プロセスがあります。
ここでは、スポーツ安全保険の具体的な請求の流れを詳しく紹介していきます。
事故通知の3つの方法
スポーツ安全保険では、事故が発生した際に保険会社へ通知する方法として、主に3つの選択肢があります。
- スポあんネットでオンライン通知
- 事故通知ハガキ
- 電話による事故通知
それぞれ簡単に紹介していきます。
1. スポあんネットでオンライン通知
1つ目は「スポあんネット」を利用したオンライン通知です。
スポーツ安全協会のウェブサイト「スポあんネット」にアクセスし、メインメニューの「事故通知」から手続きを進めましょう。
PC画面では画面左側に、スマホやタブレットでは画面右上の三本線をタップするとメインメニューが表示されます。
手続きは以下の流れで進めましょう。
- 傷害保険か突然死葬祭費用保険かを選択
- 事故発生日と負傷者の氏名を入力
- 負傷者の情報(氏名、住所、電話番号)や事故の詳細を入力
- 入力内容を確認して送信
2. 事故通知ハガキ
2つ目は「事故通知ハガキ」を利用する方法です。
スポあんネットを利用しない場合は、事故通知ハガキに必要事項を記入して東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ郵送します。
事故通知ハガキがない場合は、普通のハガキに以下の情報を記入して送ることも可能です。
- 団体名と団体代表者の氏名、電話番号
- 負傷者の住所、氏名、年齢、電話番号
- 加入依頼番号や加入手続日、加入区分
- 事故の日時、場所、詳細状況
- 傷害の内容と医療機関名、入院の有無
3. 電話による事故通知
3つ目は「電話」による通知方法で、賠償責任保険の事故通知ではこの方法が必須となっています。
法律上の賠償責任を負うおそれのある事故が発生した場合は、スポあんネットや事故通知ハガキではなく、必ず電話で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーに連絡する必要があるので注意しましょう。
書類送付から支払いまでの流れ
事故通知を行うと、その後の保険金請求手続きが始まります。
流れとしてはまず、事故通知後に東京海上日動から被保険者(負傷者)宛てに保険金請求に必要な書類一式が直接送付されます。
この書類一式には、保険金請求書や記入方法の説明などが含まれているので確認しましょう。
保険金請求書には、負傷者の情報、事故状況、治療状況などを記入します。
事故日時点での団体代表者の記名・捺印が必須ですので、漏れがないように注意しましょう。
また、未成年者が被保険者の場合は、保険金請求書に保護者の署名も必要となりますので忘れないようにしてください。
入院・通院の保険金請求額の合計が30万円以下の場合は、東京海上日動からの特別な求めがない限り、原則として医師の診断書の提出は不要です。
診断書取得の費用(自己負担)を節約できるのは嬉しいポイントですよね。
代わりに、以下の書類を提出します。
- 保険金請求書(治療状況欄に記入)
- 医療機関の領収書または診察券のコピー
- その他必要書類(入通院申告書など)
必要書類がすべて揃ったら、指定された東京海上日動の窓口へ送付しましょう。
書類に不備がなければ審査が行われ、問題なく通過すれば指定の口座に保険金が振り込まれる流れです。
スポーツ安全保険では、入院は1日あたり4,000円、通院は1日あたり1,500円が支払われます。
地域別窓口情報
スポーツ安全保険の請求手続きを進める際に重要となるのが、地域ごとに設置されている窓口情報です。
東京海上日動では、全国を複数のエリアに分け、それぞれに専用のスポーツ安全保険コーナーを設けています。
北海道地域
| 窓口名 | 東京海上日動 北海道スポーツ安全保険コーナー |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-789-027 |
| TEL | 011-271-7432 |
| 住所 | 〒060-8531 札幌市中央区大通西3-7 |
東北地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
| 窓口名 | 東京海上日動 東北スポーツ安全保険コーナー |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-789-037 |
| TEL | 022-225-6326 |
| 住所 | 〒980-8460 仙台市青葉区中央2-8-16 |
関東・甲信越地域(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
| 窓口名 | 東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-789-047 |
| TEL | 03-6632-0479 |
| 住所 | 〒105-8551 東京都港区西新橋3-9-4 |
その他の地域(東海、静岡、北陸・近畿、中国・四国、九州)にもそれぞれ専用の窓口が設置されています。
スポーツ安全保険コーナーはいずれも平日9時から17時まで対応しており、事故通知や保険金請求に関する相談を受け付けているので安心です。
自分の地域の担当窓口を事前に把握しておくことで、請求手続きが必要になった際に慌てずに対応できるでしょう。
特殊事例の対応方法
スポーツ安全保険の請求において、通常の傷害保険請求とは異なる対応が必要となる特殊なケースもあります。
賠償責任保険の請求手続き
先述した通り、スポーツ活動中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合など、法律上の賠償責任を負うおそれがある事故が発生した場合は、必ず電話で東京海上日動に連絡する必要があります。
示談交渉は被保険者(加害者)自身が行いますが、示談に際しては事前に東京海上日動と十分に相談してください。
東京海上日動の承認を得ずに示談をすると、示談金額の全部または一部について保険金が支払われない可能性があるので注意しましょう。
突然死葬祭費用保険の請求手続き
スポーツ活動中に急性心不全や脳内出血などで突然死した場合の請求手続きも特殊なケースです。
この場合も通常の傷害保険と同様に、スポあんネットの事故通知機能または事故通知ハガキを使って東京海上日動に連絡します。
保険金請求書は、亡くなった方のご親族代表宛に送付される流れになっています。
事故通知が遅れた場合
事故通知は事故発生後速やかに行うことが原則ですが、やむを得ない事情で通知が遅れた場合でも、事実関係が確認できれば支払いの対象となる可能性があります。
ただし、保険金請求権には3年の時効があるため、これを経過すると支払いを受けられなくなることがあるので注意が必要です。
学校関係の団体による請求
学校関係の団体が保険金請求を行う場合には、学校長による「学校管理下外の証明書類」が必要となる場合があります。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付との関係で必要となる書類なので確認しておきましょう。
このような特殊事例に対しては、それぞれの状況に応じた適切な対応をする必要があります。
不明な点がある場合は、早めに地域の東京海上日動スポーツ安全保険コーナーに相談することをおすすめします。
【要チェック!】スポーツ保険請求時に確認すべきこと

スポーツ安全保険の請求手続きの基本的な流れを理解したところで、実際に請求を行う際に見落としがちなポイントをチェックしておきましょう。
スポーツ保険の請求手続きは適切な流れで進めないと、保険金が減額されたり、最悪の場合は支払われなくなったりするケースもあります。
ここからは、スポーツ保険の請求プロセスをよりスムーズに進めるための重要ポイントと、うっかりミスを防ぐためのチェックリストを紹介します。
請求の流れに沿った知識を押さえて、確実に保険金を受け取りましょう。
時効対策チェックリスト
スポーツ保険の請求において最も注意すべき点の一つが「時効」です。
保険金請求権には3年の時効があり、この期間を過ぎると保険金を受け取る権利が消滅してしまいます。
以下のチェックリストを参考に、時効を避けるための対策を講じましょう。
- □ 事故発生日を正確に記録し、カレンダーやスマホなどに保存しておく
- □ 事故発生後、速やかに(できれば1週間以内に)事故通知を行う
- □ 事故通知を行った日付と方法(オンライン、ハガキ、電話)を記録しておく
- □ 保険会社から請求書類が届いたらすぐに内容を確認し、必要事項を記入する
- □ 治療が長期にわたる場合でも、3年以内に一度保険会社に状況を連絡する
- □ 複数の医療機関にかかった場合は、それぞれの治療期間を記録しておく
- □ 事故から2年経過した時点で未請求の場合は、早急に手続きを開始する
特に注意したいのは、「事故通知」と「保険金請求」は請求の流れの中で別のステップだということです。
事故通知を行っただけでは時効は中断されません。
何らかの事情で請求手続きの流れが遅れる場合でも、事実関係が確認できればお支払いの対象となる可能性はありますが、3年の時効を過ぎると権利が消滅するリスクが高まります。
治療が長期化する場合や、後遺障害が残る可能性がある場合は、治療完了を待たずに一度保険会社に相談することも検討しましょう。
書類不備防止のポイント
スポーツ保険の請求プロセスでよくある躓きの一つが、書類の不備です。
書類に不備があると審査の流れが滞り、保険金の支払いも遅延します。
以下のポイントを押さえて、スムーズな請求手続きの流れを心がけましょう。
書類作成時の基本チェックリスト
- □ 保険金請求書に事故日時点での団体代表者の記名・捺印があるか
- □ 被保険者が未成年の場合、保護者の署名があるか
- □ 入通院日数や治療期間の記載に誤りがないか
- □ 請求金額の計算に誤りがないか
- □ 傷病名や事故状況の記載が医療機関の診断と一致しているか
- □ 保険金振込先の口座情報が正確か
よくある不備とその対策
団体代表者関連の不備
団体代表者自身やその家族が被保険者の場合、団体代表者・家族以外の団体員(団体員名簿に記載されている成人の方)の記名・捺印が必要です。
このルールを知らずに書類を提出すると、請求の流れが中断されて差し戻しの原因となります。
入通院保険金請求額が30万円以下の場合
診断書の代わりに、保険金請求書の治療状況欄への記入と医療機関の領収書または診察券のコピーで対応可能です。
不必要に診断書を取得して費用負担が増えないよう注意しましょう。
賠償責任保険関連の書類
示談交渉は被保険者自身が行いますが、示談前に必ず東京海上日動と相談することが重要です。
東京海上日動の承認なしで示談すると、保険金支払いの流れに支障をきたし、保険金が支払われないケースがあります。
スポーツ保険の請求の流れに際してよくある疑問

スポーツ保険の請求手続きの流れを進める中で、多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
請求の流れをより理解するための参考にしてください。
Q. 事故通知が遅れた場合、保険金は支払われませんか?
A. 事故通知は速やかに行うことが原則ですが、何らかの事情で通知が遅れた場合でも、事実関係が確認できれば支払いの対象となることがあります。
ただし、保険金請求権には3年の時効があるため、この期間を過ぎると支払われない可能性が高くなります。
Q. 複数の医療機関を受診した場合、どのように請求すればよいですか?
A. 複数の医療機関を受診した場合でも、1回の事故につき1回の請求手続きで対応できます。
請求書には、すべての医療機関での治療内容と期間を記入し、それぞれの医療機関の領収書または診察券のコピーを添付してください。
請求の流れ自体は変わりません。
Q. スポーツ安全保険と学校の災害共済給付の両方に加入している場合はどうすればよいですか?
A. 学校関係の団体が保険金請求を行う場合、学校長による「学校管理下外の証明書類」が必要となる場合があります。
これは日本スポーツ振興センターの災害共済給付との関係で必要となる書類です。
両方から給付を受ける場合の流れは少し複雑になりますので、学校と相談の上、適切に手続きを進めましょう。
Q. インターネット加入と用紙での加入で請求方法に違いはありますか?
A. インターネット加入(スポあんネット)の場合は、オンラインでの事故通知が可能です。
一方、用紙での加入の場合は事故通知ハガキや電話での通知となります。
基本的な請求の流れは同じですが、事故通知の方法が異なりますので注意しましょう。
Q. 保険金支払いまでの流れと期間はどのくらいですか?
A. 書類提出から保険金支払いまでの流れは、書類に不備がなければ短期間で処理されることが多いです。
ただし、事故の状況や傷害の程度によって異なりますので、具体的な日数は一概には言えません。
不安な場合は、担当の東京海上日動スポーツ安全保険コーナーに問い合わせると良いでしょう。
請求手続きの流れに不明点がある場合は、各地域の東京海上日動スポーツ安全保険コーナーに気軽に相談してください。
専門のスタッフが丁寧に対応してくれます。
記事のまとめ

スポーツ保険の請求手続きは、事故通知から保険金支払いまで、決められた流れに沿って進めることが大切です。
特にスポーツ安全保険の申請方法をしっかり理解し、必要書類を漏れなく準備することで、スムーズな保険金請求が可能になります。
万が一の事故に備えて、加入している保険の連絡先や請求手続きの流れを今のうちから確認しておきましょう。
団体活動中のケガやトラブルは予期せぬタイミングで起こるものです。
いざという時に慌てず対応できるよう、この記事を参考に請求の手順を把握し、適切な医療費請求ができる準備をしておくことをおすすめします。
スポーツを安心して楽しむための保険制度を、ぜひ有効に活用してください。