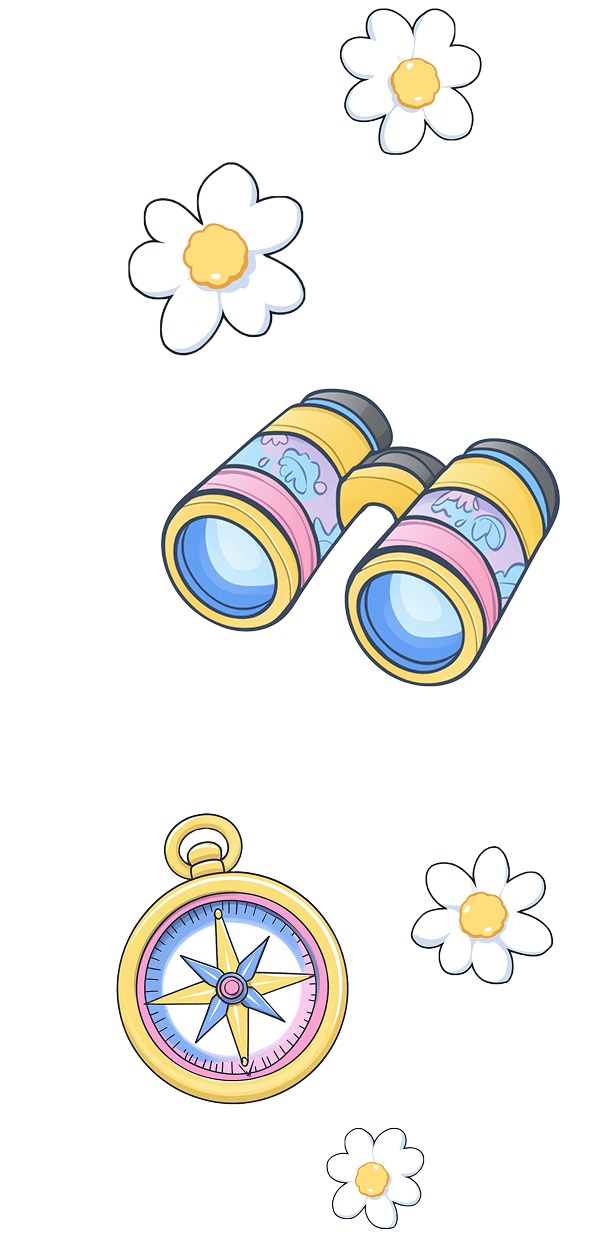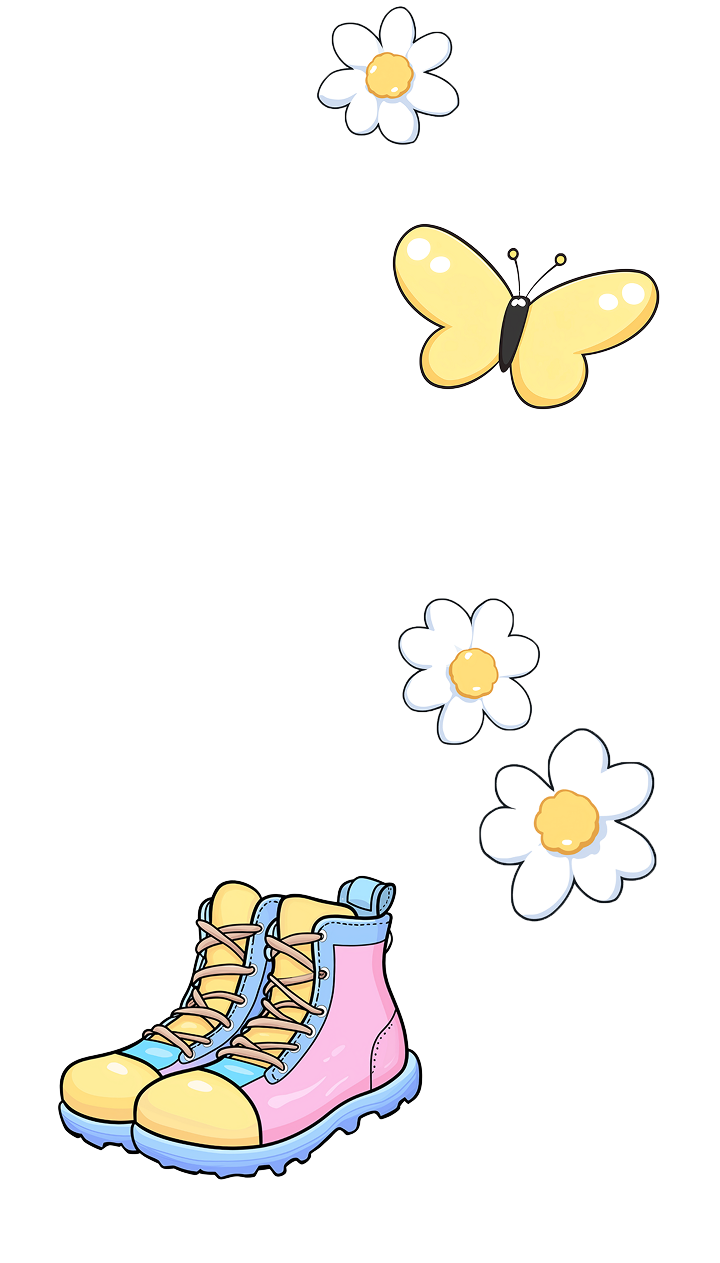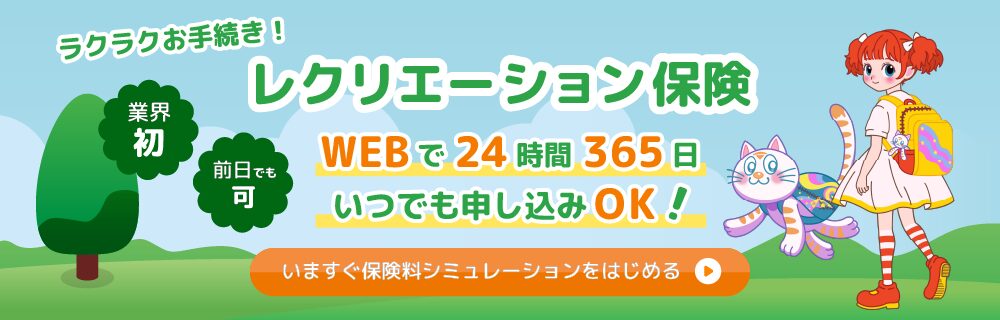「盛り上がるレクリエーション遊びって、どんなのがあるのかな?」
「初対面でも楽しめる遊びを知りたいな」
「短時間でできる、手軽な遊びはないだろうか?」
こんなふうに、レクリエーション遊びについて悩むことはありませんか?
レクリエーションがあると、場の空気がほぐれて、自然な会話も生まれやすくなります。
しかし、いざ何かやろうと思っても、どんな遊びを選べばいいか迷ってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、誰でも気軽に楽しめて、すぐに取り入れやすいレクリエーション遊びを紹介します。
具体的には、この記事では次のような遊びを取り上げています。
- 会話力や観察力が育つレクリエーション遊び
- 身近な道具でできる、準備がいらないレクリエーション遊び
- 初対面でも盛り上がる定番&ちょっと変わったレクリエーション遊び
「ノーカタカナゲーム」や「新聞紙島」など、実際の例を通して、選ぶときのポイントや楽しみ方もわかります。
レクリエーションの魅力を知って、日常やイベントの中で活かしてみてください。
遊びを通して、場の雰囲気がぐっと明るくなるはずです。
みんなで楽しめる!レクリエーション遊び13選
 ここからは、みんなで盛り上がれるレクリエーション遊びを13個ご紹介します。
どれもすぐに始められるものばかりで、レクリエーション初心者でも安心です。
ここからは、みんなで盛り上がれるレクリエーション遊びを13個ご紹介します。
どれもすぐに始められるものばかりで、レクリエーション初心者でも安心です。
年齢や場面を問わず楽しめるので、ぜひ気になるものから試してみてください。
NGワードゲーム
相手にNGワードを言わせるように会話を進めるレクリエーションです。
たとえば、NGワードが「パソコン」の場合、「パソコンと電話、どちらか一つを捨てるなら?」と質問します。
相手がうっかり「パソコン」と答えたら、言わせた側の勝ちになります。
NGワードを決めるときには、「はい」や「いいえ」など、つい言ってしまいがちな相槌を選ぶのもおすすめです。
わかっていても、会話のテンポが速くなるとつい口にしてしまい、笑いが生まれて盛り上がることがよくあります。
雑談とは違って、戦略的に言葉を選びながら話す必要があるため、自然と会話力や観察力が鍛えられます。
頭を使って楽しめるので、仲間同士での遊びにもぴったりです。
新聞紙島
新聞紙を島に見立てて、その上だけを歩いてゴールを目指す、体を使ったレクリエーションです。
ルールは簡単で、新聞紙の上以外に足がついてしまうとアウトです。
2枚の新聞紙を交互に床に置いて、島から落ちないように進んでいきましょう。
身近な新聞紙があれば、すぐに遊べるのが良いところです。
遊ぶ際は、床が滑りやすくないか確認し、必要に応じて靴下を脱ぐなど安全に配慮しましょう。
子どもたちが遊ぶ時には、「海に落ちたらサメに食べられちゃうよ!」という設定にすると、想像力が膨らんで、より一層楽しめます。
牛タンゲーム
「牛」と声に出し、「タン」で手をたたくリズム遊びです。
言葉と動きを合わせて進める、シンプルでも集中力が求められるレクリエーションです。
基本の流れは「牛・タン・牛・タン・牛・タン・タン」です。「牛」のときは声だけ、「タン」のときは声を出さずに手をたたきます。
リズムに乗って順番に続けていくのがコツです。
ターンを重ねるごとに、最後の「タン」の回数が一つずつ増えていきます。
たとえば、3ターン行うとすると、言葉のリズムは次のようになります。
- 1ターン目:「牛・タン・牛・タン・牛・タン・タン」
- 2ターン目:「牛・タン・牛・タン・牛・タン・タン・タン」
- 3ターン目:「牛・タン・牛・タン・牛・タン・タン・タン・タン」
回数が増えるにつれて、どんどんややこしくなり間違いやすくなります。
ミスしてしまっても、それが笑いにつながることが多く、遊びの楽しさの一部になっています。
3〜5人ほどで遊ぶのにちょうどよく、短時間でも気軽に楽しめるレクリエーションです。
リズムを速くしたり、誰かの名前を入れてアレンジすれば、さらに盛り上がるでしょう。
震源地ゲーム
みんなで輪になって、誰が最初に動きを始めたのかを当てるレクリエーションです。
基本の流れはこんな感じです。
- 鬼を1人決めて、いったん輪の外に出す
- 輪の中で「震源地役」を1人こっそり決める
- 震源地役が拍手や手を振るなどの動きを始める
- 他の子たちは、その動きを見てすぐに真似する
- 鬼が戻ってきて、誰が最初に動きを始めたかを観察して当てる
観察力と表現力が必要な遊びなので、目立たないように動きを変えたり、工夫しながら参加するとおもしろさが増します。
「ジャンプ」「拍手」「手を振る」などの簡単な動きから始めると、初めてでも入りやすいです。
慣れてくると、自分で動きを考える余裕も出てきます。
繰り返すうちに、周りを見る力や判断力も自然と身についていきます。
人数に合わせてルールを調整できるので、グループ活動やイベントでも使いやすいレクリエーションです。
おばあちゃん伝言ゲーム
笑ったり歯を見せたりしたら負けになる、ちょっと変わった伝言ゲームです。
「おばあちゃんのしゃべり方」で伝言をしていくのがルールで、その姿がとにかく面白いのに、笑ってはいけないというのがこのゲームの最大のポイントです。
普通の伝言ゲームと同じく、お題を順番に伝えていきますが、しゃべり方は「おばあちゃん風」にしなければなりません。
さらに、話している間に笑ってしまったり、歯を見せてしまうと即アウトです。
例えば、「きゃりーぱみゅぱみゅがプリンをおいしく食べたよ」といった言いにくいお題を使うと、声がふるえて伝言がめちゃくちゃになっていくのが本当におかしくなります。
演技力と我慢強さが試される、笑いをこらえながら盛り上がれる遊びです。
リズム4ゲーム
4拍子のリズムに合わせて、名前と数字をテンポよく言っていくレクリエーションです。
親役の人が、リズムに合わせて他の人の名前と数字を指定し、指名された人はその回数だけ自分の名前を言います。
たとえば「ひろき、2!」と言われたら、呼ばれた「ひろき」本人が、次のリズムに合わせて「ひろき、ひろき」と2回自分の名前を言います。
ルールはシンプルですが、間違えずにリズムに乗るのは意外と難しく、だんだんスピードが上がるとミスも増えてきます。
リズムに乗って遊ぶのが楽しく、みんなで息を合わせられるので、にぎやかな場にぴったりの遊びです。
色取り忍者ゲーム
リーダーが色を指定し、参加者はその色の物にすばやく触れます。
触るのが遅れたり、周りにその色が見つからなかった人はアウトになります。
たとえば「青!」と言われたら、すぐに青いペンや服など、身近にある青いものに触ります。全員が同時に動き出すので、少しの判断の遅れが命取りです。
一番最後になってしまった人や、触れる物が見つけられなかった人がその回の負けとなり、ゲームから抜けます。
ゲームは何回か繰り返して、最後まで残った人が優勝です。
「ピンク」や「白」など、意外な色を選ぶと難しくなり、盛り上がります。
観察力と反応の速さが試されるので、みんなでドタバタしながら遊べて、とても楽しいゲームです。
グループジャグル
円になってボールを投げ合う、反応力とチームワークを試すレクリエーションです。
参加者全員が円を作り、1人がボールを誰かに投げます。受け取った人は別の人に投げ、全員が「誰から誰へ投げるか」を決めて固定します。
その順番を覚えて、同じパターンでボールを回します。
慣れてきたら2個、3個とボールを増やすと、同時に投げ合うと難易度が上がり、遊びながら集中力や協力が求められます。
8〜20人程度で遊べて、用意するのは柔らかいボールだけなので非常に手軽。
15分ほどの短時間でもしっかり盛り上がる遊びです。
人間ビンゴ
質問に当てはまる人を探してサインをもらう、会話を楽しむレクリエーションです。
ビンゴカードには「今日朝ごはんがパンだった人」「兄弟が3人以上いる人」などの質問が書かれています。
参加者はクラスメイトに声をかけ、当てはまる人からサインをもらいながらマスを埋めていきます。
同じ人に2マス以上サインをもらうことはできません。
途中で班ごとに協力する時間を取り入れることで、グループ内のつながりも深まりやすくなります。
最後にビンゴの数を競ったり、質問の答えを発表したりすることで、よりいっそう盛り上がります。
話すのが得意でない人も自然と会話できるので、学級づくりにも取り入れやすい遊びです。
英会話伝言ゲーム
英語のフレーズをリレー形式で伝えていく、英語×遊びのレクリエーションです。
最初の人だけが英語の音声を聞き、そのフレーズを隣の人に小声で伝えます。
以降、聞いた通りの英語を次々に伝えていき、最後の人がフレーズを発表し、その意味を日本語で答えます。
うまく伝わらないと、まったく違うフレーズになってしまうことも。
たとえば「It was a nice place.」が「Nice waitress」に変わってしまうなど、笑える展開がよく起こります。
聞き取りと記憶力が試されるうえ、英語にも親しめる遊びです。
授業の導入や休憩時間のレクリエーションとしても使いやすいです。
漢字人物連想当てゲーム
「漢字人物連想当てゲーム」は、有名な人物を1文字の漢字で表し、その人物が誰かを当てる遊びです。
まず、お題となる人物を1人決めます。
「ペリー」や「織田信長」など、みんなが知っている人がいいでしょう。
お題は答える人には内緒にして、他の人だけに伝えておきます。
次に答える人を1人決めたら、残りの人たちはその人物に関係する漢字を1文字ずつ出します。
ただし、名前に使われている漢字はNGです。
「ペリー」なら「船」や「浦」などがヒントになります。
漢字が出揃ったら、答える人はヒントをもとに人物名を当てます。
正解すれば1ポイント。
全員が順番に答える役をして何周かしたあと、いちばん多く正解した人が勝ちです。
正解が出た後は、どうしてその漢字を選んだのかを話し合うと、意外な発想があって盛り上がります。
交代しながら遊べば、みんなで楽しめるシンプルなゲームです。
ノーカタカナゲーム
「ノーカタカナゲーム」は、カタカナ言葉をカタカナを使わずに説明して、何のことかを当てるレクリエーションです。
まず、「アイス」「ハンバーガー」など、カタカナの言葉をひとつ選びます。
出題者だけが内容を確認し、答える人には伝えません。
お題を決めたら、その言葉をカタカナを使わずに説明します。
たとえば「エアコン」なら「部屋につけて暖かい風や冷たい風を出すもの」などと表現します。
説明を聞いた人が正解を言えたら成功です。言い換えの工夫やひらめきが問われる、頭を使う遊びです。
おうちにあるものしりとり
オンラインで行う、家の中を使ったしりとり遊びのレクリエーションです。
前の人の言葉の最後の文字から始まる物を、自分の部屋の中から探して見せ合います。
たとえば「めがね」→「ねこ」→「こたつ」のように、言葉をつなげながら物を探していきます。
見つけた物は、カメラ越しに見せたり、その場に置いたりして相手に伝えましょう。
1人あたり30秒〜1分ほどの制限時間を設けると、テンポよく進んで盛り上がります。
画面越しに部屋の様子がちらっと見えるのも、この遊びならではの楽しさです。
家にある身近な物を使うので、特別な準備はいりません。オンラインだからこそできる、子どもから大人まで一緒に楽しめるレクリエーションです。
Q&A|レクリエーション遊びに関するよくある質問
 レクリエーション遊びを取り入れるとき、「初対面でも盛り上がるかな?」「ルールってうまく説明できるかな?」と、不安に思うことがあるかもしれません。
レクリエーション遊びを取り入れるとき、「初対面でも盛り上がるかな?」「ルールってうまく説明できるかな?」と、不安に思うことがあるかもしれません。
ここでは、よくある疑問にわかりやすくお答えします。
初対面同士でも盛り上がる遊びはある?
「人間ビンゴ」や「ノーカタカナゲーム」は、話すきっかけが生まれやすいので、初めて会う人同士でも自然と会話が広がります。
また、「震源地ゲーム」や「色取り忍者ゲーム」など、体を動かす遊びも緊張をほぐして距離を縮めるのに向いています。
どちらも、初対面の場を和やかにするのにぴったりのレクリエーションです。
安全に気をつけるにはどうすればいい?
周りにぶつかりそうな物がないかを確認したり、滑りやすい場所では靴下を脱いだりと、環境を整える工夫が大切です。
また、「押さない・走らない」といったルールをあらかじめ決めておくと、安心して楽しめます。
安全への気配りがあると、みんながリラックスして参加できます。
ルール説明が苦手でも大丈夫?
もしルールを説明するのが苦手でも、最初にお手本を見せたり、一緒にやってみたりすれば自然と覚えてもらえます。
一度経験すればわかる遊びが多いので、言葉だけで説明しようとせず、流れの中で伝えていくのがおすすめです。
気負わずに、まずは一緒に始めてみることが大切です。
短時間で終わる遊びの例は?
「牛タンゲーム」や「ノーカタカナゲーム」は、5〜10分ほどで気軽に楽しめます。
さらに、「新聞紙島」や「グループジャグル」も、時間を短く調整しやすいため、すきま時間にぴったりです。
ちょっとした合間に遊びを取り入れるだけで、その場がぐっとなごやかになります。
まとめ
 この記事では、短時間でできて盛り上がるレクリエーション遊びを13個紹介してきました。
この記事では、短時間でできて盛り上がるレクリエーション遊びを13個紹介してきました。
どれも準備がほとんどいらず、気軽に楽しめるものばかりです。
気になった遊びがあれば、ぜひ取り入れて、楽しい時間を過ごしてみてください。
なお、イベントや行事でレクリエーションを行う際には、みんレクの「レクリエーション傷害保険」の活用を検討してみるのもいいかもしれません。
1日1名あたり約29円から加入でき、ケガのほか熱中症や食中毒にも対応しています。
ネットから前日まで申し込めるので、手軽に備えることができます。
安全面にも気を配って、みんなが安心して楽しめるレクリエーションを目指しましょう。
※参照 レクリエーション傷害保険 | みんレク https://xn--cbkxbye7k.com/lp02/