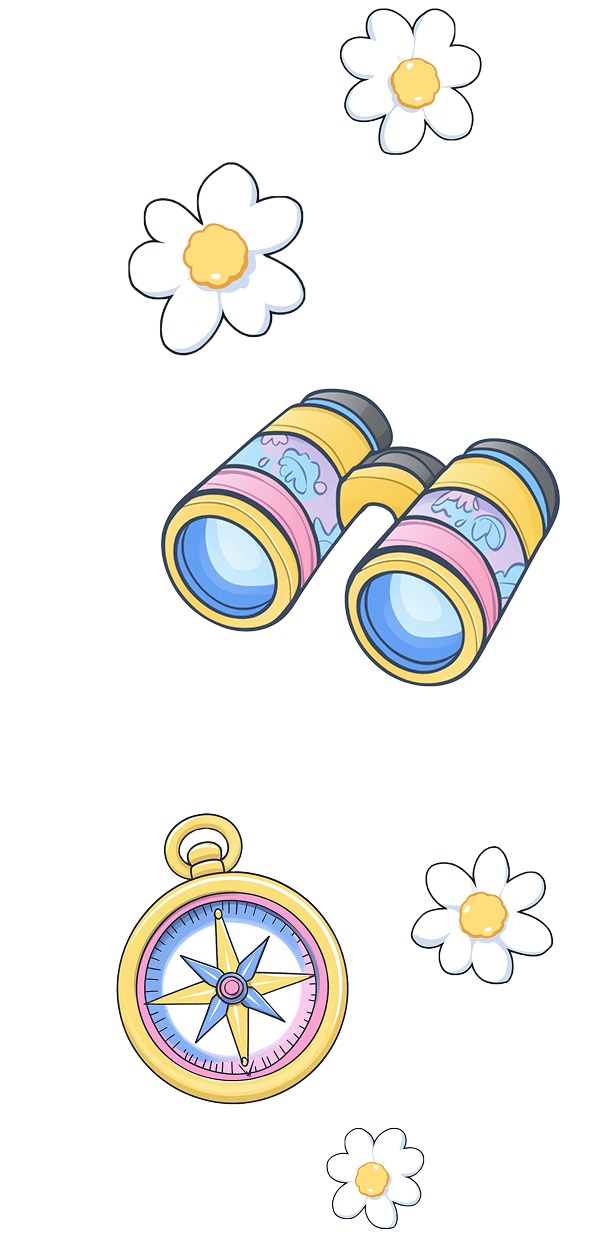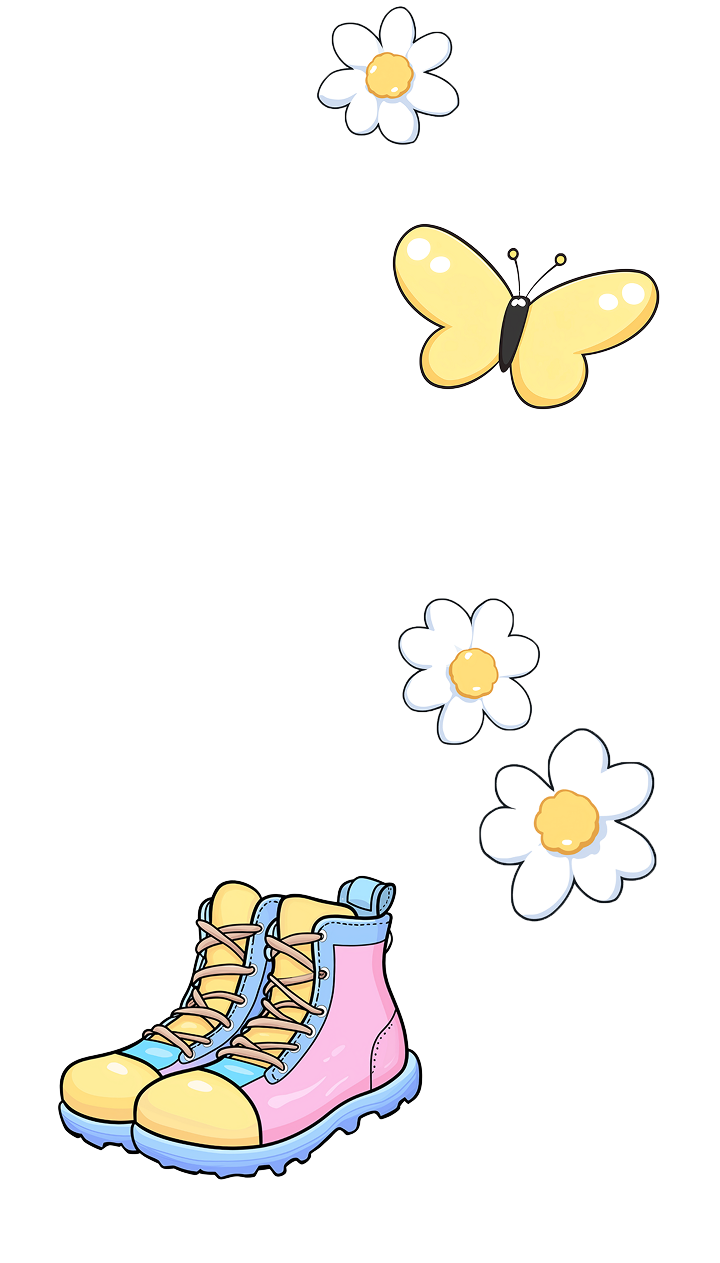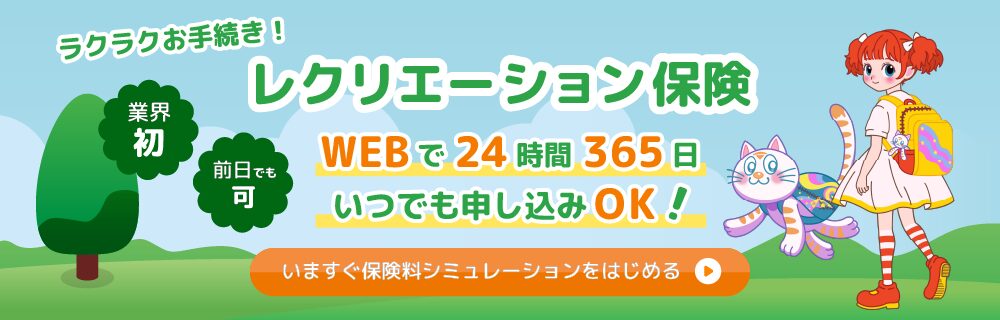「『部活動の地域移行』って聞くけど、結局、保護者の負担が増えるだけじゃないの?」
「うちの子の部活動、これからどうなっちゃうんだろう?」
そんな不安や疑問を解消し、子どもたちにとっても、先生や保護者の皆さんにとってもより良い形を目指すのが『部活動の地域移行』という改革です。
この記事では、部活動の地域移行について、保護者と教員それぞれの視点から、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 教員の働き方はどう変わる?
- 保護者の費用や送迎の負担は増える?
- 子どもにとってのメリット・デメリット
この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、家庭や学校現場で具体的に何がどう変わるのか、部活動の地域移行の全体像がわかります。
まずは正しい知識を身につけて、これからの変化に備えましょう。
部活動の地域移行とは?押さえておくべき3つの基本

部活動の地域移行について理解を深めるために、まずはその背景や目的、今後のスケジュールといった基本的なポイントを解説します。
なぜ今、部活動の地域移行が進められているのか?
部活動の地域移行が進められている背景には、二つの大きな理由があります。
一つは「少子化」、もう一つは「教員の働き方改革」です。
生徒の数が減り、学校だけでは部活動を維持するのが難しくなっていること。
そして、部活動の指導が教員の大きな負担となり、本来の授業などに集中できない状況があること。
この二つの課題を地域全体で補い、部活動を持続可能な形に整えていく狙いがあります。
「いつから」本格的に始まる?国の推進期間と今後の見通し
部活動の地域移行は、ゆっくりと段階的に進められています。
まず、2023年度から2025年度までの3年間を、地域への移行を始めるための「改革推進期間」としました。
しかし、地域ごとの準備にはもっと時間が必要なことが分かり、2026年度からは新たに6年間の「改革実行期間」が設けられています。
前半の3年間(2026~2028年度)には、まだ着手していない自治体でも、休日の部活動については地域での取り組みを始めるよう求められています。
また、名前も「地域移行」から「地域展開」へと変わりました。
このことは、学校から完全に切り離すのではなく、地域の実情に合わせて協力していく、より柔軟な考え方を示すためのものです。
部活動の地域移行の用語整理として理解しておくとよいでしょう。
※参照 全国こども政策主管課長会議 文部科学省
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b1ba8054-23a8-4ad2-94bb-d0f6e0a03c51/ea827811/20250314-councils-kodomoseisaku-syukankacho-b1ba8054-3100.pdf
国が示すガイドラインの主なポイント
部活動の地域移行に関して、国が定めたガイドラインには、新しい地域クラブ活動を安心して行えるようにするための大切なルールが示されています。
活動の運営は市区町村や地域のNPO、民間企業などが担い、指導は専門的な知識や資格を持つ地域の人が行うことを基本としています。
また、子どもたちの心と体の健康を守るため、次の点を求めています。
- 週2日以上(平日1日・週末1日)の休養日を設ける
- 健康管理・事故防止の徹底(体罰・ハラスメントの根絶を含む)
- 部活動への強制加入は行わない
大会については、地域クラブ活動の会員も参加できるよう参加資格が見直され、生徒が不利にならないよう配慮が進められています。
※参照 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 総合的なガイドライン【概要】 スポーツ庁・文化庁
https://www.mext.go.jp/sports/content/20221227-spt_oripara-000026750_1.pdf
【教員向け】部活動の地域移行で働き方はどう変わる?

部活動の地域移行で、先生の働き方がどうなるのか、不安に感じていませんか?
ここでは、負担が減る部分と、新たに求められる役割の両面を具体的に解説していきます。
休日の指導義務がなくなり、ワークライフバランスが改善される
地域移行によって、先生にとって最も大きく変わるのは、休日の指導が義務ではなくなる点です。
国の方針では、「休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事しないこと」と明確に定められています。
週末を部活動の指導や大会の引率に費やしてきた先生は、その負担から解放されることになるのです。
※参照 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について | 文部科学省
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200902-spt_sseisaku01-000009706_3.pdf
部活動の指導が「義務」から「選択」へと変わる。
このことが、働き方における最も本質的な変化だと言えるでしょう。
もちろん、休日も関わりたいと希望する先生は、兼職兼業の許可を得た上で、地域クラブの指導者として有償で関わる道も用意されています。
※参照 運動部活動の地域移行について | スポーツ庁
https://www.mext.go.jp/content/20220727-mxt_kyoiku02-000023590_2-1.pdf
専門外の部活動顧問を担当する負担から解放される可能性がある
地域移行が進むことで、先生の時間的な負担に加えて精神的な負担も和らぐと考えられます。
これまでは、先生自身の専門分野や指導経験に関わらず、学校の都合で部活動の顧問を割り当てられることが少なくありませんでした。
専門外の活動を指導することへの不安は、大きなストレスとなっていたのではないでしょうか。
地域移行によって指導が地域の専門的な指導者へ移ることで、先生はこの種の負担から解放されます。
その分、自身の専門性を活かせる教科指導や、生徒一人ひとりとの関わりに、より多くの時間を注げるようになるのです。
学校と地域クラブをつなぐ連絡・調整といった新たな役割が求められる
部活動の指導という役割が減る一方で、学校と地域クラブをつなぐ橋渡し役という新たな役割が生まれます。
具体的には、地域クラブの活動内容を生徒や保護者に伝えたり、学校施設の利用スケジュールを調整したりする業務が想定されます。
ただし、この新たな役割が校務分掌として明確に位置づけられず、勤務時間内で適切に評価されなければ「見えないサービス残業」になりかねません。
地域移行の成功は、学校・地域・行政が適切に役割を分担できるかにかかっています。
※参照 令和6年度 全国こども政策主管課長会議 | 文部科学省
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b1ba8054-23a8-4ad2-94bb-d0f6e0a03c51/ea827811/20250314-councils-kodomoseisaku-syukankacho-b1ba8054-3100.pdf
【保護者向け】費用や送迎は?保護者の負担は増えるのか解説

部活動の地域移行で、家計への影響や送迎の手間が心配になっていませんか?
ここでは、部活動の地域移行によって新たに発生する負担と、逆に軽減される負担について解説していきます。
指導料や施設利用料など、金銭的な負担が増える可能性がある
指導料や施設利用料など、金銭的な負担が増える可能性があります。
地域移行で最も大きく変わるのが費用の負担で、活動にかかる費用を参加する家庭が分担して支払う形が基本になるためです。
具体的には、以下のような費用が発生します。
- 指導者への謝金
- クラブの会費
- 施設利用料
- 安全対策費(保険料など)
金額は地域によって異なり、月会費が2,000円程度、年間の安全対策費(保険料等)が800円程度というケースがあります。
なお自治体によっては、指導者の報酬を公費で負担したり、困窮家庭向けに減免制度を設けたりしています。お住まいの地域の支援内容を確認しておくと安心です。
※参照 中学校の部活動地域移行に係るQ&A | 兵庫県播磨町
https://www.town.harima.lg.jp/gakkokyoiku/kyoiku/documents/ikouqa.pdf
活動場所への送迎が新たに必要になるケースも
複数の学校から生徒が集まる形になるため、活動の拠点が自宅や学校から離れた場所になることがあります。
距離がある場合は、家族による送迎が必要になる場面も考えられます。送迎は時間の拘束に加えて、ガソリン代などの経済的負担も発生します。
一方で、解決策も各地で検討されています。
スクールバスの活用、公共交通機関の時刻に合わせた練習時間の設定、乗合タクシーや貸切バスの運行など、地域に合わせた移動手段の整備が進んでいます。
こうした取り組みが増えることで、保護者の負担を抑えつつ参加しやすい環境が整いつつあります。
部活動の地域移行の実務上の課題として押さえておきましょう。
指導者との直接の連携で、お茶当番などの役割がなくなることも
地域移行によって、保護者の負担が軽くなる場合があります。
代表的なのが、お茶当番の廃止です。専門の指導者や運営団体が活動を管理するため、保護者が現場で担ってきた役割が不要になります。「お茶当番なし」を明確に示す地域クラブも出てきています。
一方で、指導者と直接やり取りをしたり、保護者会で運営に参加したりする形で、関わり方が変わっていきます。
会費を支払う対等な立場として、クラブを支える姿勢が求められます。
保護者が現場から離れる一方で、支援の形は残るため、負担の質が変化する点を理解しておくことが大切です。
メリット・デメリットを徹底比較|子どもにとっての変化とは?

地域移行によって、子どもたちの部活動はどう変わるのでしょうか。
ここでは、部活動の地域移行がもたらす専門的な指導や選択肢の広がりといったメリットと、地域格差や移動負担などのデメリットを解説します。
メリット:専門的な指導者から質の高い指導を受けられる
地域移行の大きなメリットは、専門的な知識を持つ指導者から学べる機会が増えることです。
これまでは、その種目の専門家ではない先生が顧問を務めるケースも少なくありませんでした。
地域クラブでは、元プロ選手や競技経験が豊富な指導者が教えてくれることが期待されています。
国も指導者資格の取得支援を進めており、指導の質を高める体制づくりが進んでいます。
メリット:学校の枠を超えて多様な種目を選択できるようになる
地域移行によって、子どもたちが選べる活動の幅が広がります。
少子化でチーム編成が難しい団体競技も、複数校から生徒が集まれば活動を続けられます。
学校では設置が難しかったレスリングやクラシックバレエといった種目も、地域クラブなら活動できるようになるでしょう。
自分の興味に合った活動を見つけやすくなるのは、大きな魅力と言えるでしょう。
デメリット:受け皿となる地域クラブの質や量に差が生まれる
最も心配されているのが、住んでいる場所によって受けられる活動に差が出てしまうことです。
都市部では多くの団体がある一方、地方では指導者や運営団体を見つけること自体が難しい場合があります。
また、活動費も運営主体によって無料から高額まで様々で、家庭の経済状況が参加機会を左右してしまう懸念もあります。
デメリット:活動場所の確保が難しくなり、移動時間が増える
活動する場所をどう確保するかも大きな課題です。
学校施設を使う場合、セキュリティ管理や地域住民との利用調整が必要になります。
その結果、活動場所が遠くなり、保護者の送迎負担が増えることへの心配の声が多く上がっています。
送迎が難しい家庭の子どもは、参加できる活動が限られてしまうという問題も生じています。
地域移行の現状と今後の課題

全国で進められている地域移行ですが、多くの課題も浮き彫りになっています。ここでは、現在の進捗状況と、解決すべき3つの大きな課題について解説します。
全国の進捗状況と、都市部と地方での地域差
スポーツ庁の2024年8月調査によると、2025年度には休日の部活動の54%が地域連携または地域移行を予定しており、全国的に着実な進捗が見られます。
しかし、地域によって取り組み状況には大きな差があります。
人口規模の小さい地方では過疎地域を抱える自治体も多く、指導者の確保が特に困難で、市町村の枠を超えた連携もほとんど進んでいません。
一方、都市部では指導者確保に加えて、活動を続けていくための収支バランスの構築や、保護者への理解を広げることが主な課題となっています。
地域の実情に合わせた柔軟な対応が、これから求められていくでしょう。
※参照 部活動改革の“現状”と“展望”〜有識者会議による「中間とりまとめ」〜 | スポーツ庁
https://sports.go.jp/tag/school/post-148.html
最大の課題である「指導者の確保」と質の担保
多くの自治体の悩みは、指導者不足です。スポーツ庁FAQでも、部活動指導員や外部指導者の確保が主要課題とされています。
外部指導者が集まりにくい理由として、次の不安や事情が挙げられます。
- 指導できる自信がない
- 仕事との両立が難しい
あわせて質の確保も重要です。
ガイドラインは、指導員が不足する場合の外部指導者配置、引率体制の見直し、採用や必要な研修の実施を、学校設置者の責任で進めることを示しています。
活動中の事故やトラブルにおける「責任の所在」の明確化
地域クラブでの活動は、学校の部活動とは責任の仕組みが大きく異なります。
特に、指導者個人が賠償責任を負う可能性がある点が大きな違いです。
この点が指導者の不安材料となっていましたが、国はスポーツ安全保険の内容を見直し、安全対策の整備を進めています。主な改善点は次のとおりです。
- 指導者を対象とした賠償責任保険の追加
- 生徒のけがに対する補償水準の改善(学校の保険と同程度を目指す形)
こうした見直しが進むことで、指導者・生徒ともに安心して活動しやすい環境が整いつつあります。
部活動の地域移行に関するよくある質問

最後に、部活動の地域移行に関して多くの方が抱く疑問にQ&A形式でお答えします。
地域移行に反対する意見があるのはなぜですか?
もっとも多いのは「家庭の負担が増えるのでは」という不安です。
鳥取県三朝町のアンケートでも、指導者への謝礼や保険料などを家庭が負担する形になると「経済状況によって参加できる子に差が出る」「費用が不明で不安」といった声が目立ちました。
また、「指導者が確保できるのか」「送迎など家庭の負担が増える」「学校が担ってきた役割が失われる」といった現実的な懸念も挙がっています。
※参照 中学校部活動の休日における地域移行に係るアンケートについて【結果】 | 鳥取県三朝町
https://www.town.misasa.tottori.jp/files/53590.pdf
地域のクラブ活動への加入は強制になりますか?
地域クラブへの加入は強制ではありません。
部活動は、生徒自身の「自主的・自発的な参加」が学習指導要領で原則とされており、この考え方は地域クラブでも同様に適用されます。
例えば、平日は学校の部活動だけに参加し、休日の地域クラブ活動には参加しない、といった選択も可能です。
またその逆に、平日の学校部活動には参加せず、休日だけ地域クラブで活動するという参加の仕方も認められています。
※参照 部活動地域移行(地域展開) | 奈良県
https://www.pref.nara.jp/50930.htm
活動にかかる費用は、誰がどのように決めるのですか?
部活動の地域移行における活動費用は、クラブを運営する団体が決めます。
運営主体は、NPO法人や地域のスポーツ・文化団体、市町村の教育委員会などが想定されています。
指導者への謝礼や施設利用料、安全対策としての保険加入などの実費をもとに金額が算定され、「受益者負担」を原則として参加家庭が費用を負担します。
ただし、国や自治体からの補助金がある場合は、負担が軽くなることもあります。
※参照
https://www.town.harima.lg.jp/gakkokyoiku/kyoiku/documents/ikouqa.pdf
地域クラブ運営の「万が一」に備えるレクリエーション保険
部活動の地域移行で、安全管理の責任は学校から地域の運営主体へと移ります。
万が一の事故に備え、参加者と主催者の両方を守る保険の重要性が高まっています。
こうした備えの一つが、単発のイベントにも対応できるレクリエーション保険です。 例えば「みんレク」は、1人1日あたり約29円からという手頃な掛金で加入できます。
ネットで24時間、開催日の前日まで申し込める手軽さも、忙しい運営者には心強い点です。
参加者のケガだけでなく、主催者が負う賠償責任リスクもカバーできるため、運営の備えとして検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ

この記事では、「部活動の地域移行」で何が変わるのかを解説しました。先生や保護者の皆さんの負担、そして子どもたちの活動環境がどう変化するのか、そのメリットとデメリットをわかりやすくお伝えしてきました。
先生の負担が軽くなる一方、保護者には費用や送迎の負担が増えるかもしれません。子どもたちは専門的な指導を受けられますが、地域によって選べるクラブに差が出てしまう、といった課題もあります。
部活動の地域移行について、お住まいの地域や学校からのお知らせに、ぜひ関心を持ってみてください。
部活動の地域移行でこれから何が変わるのかを知っておくだけで、安心して変化に備えられます。
みんなで子どもたちの活動をより良いものにしていきましょう。