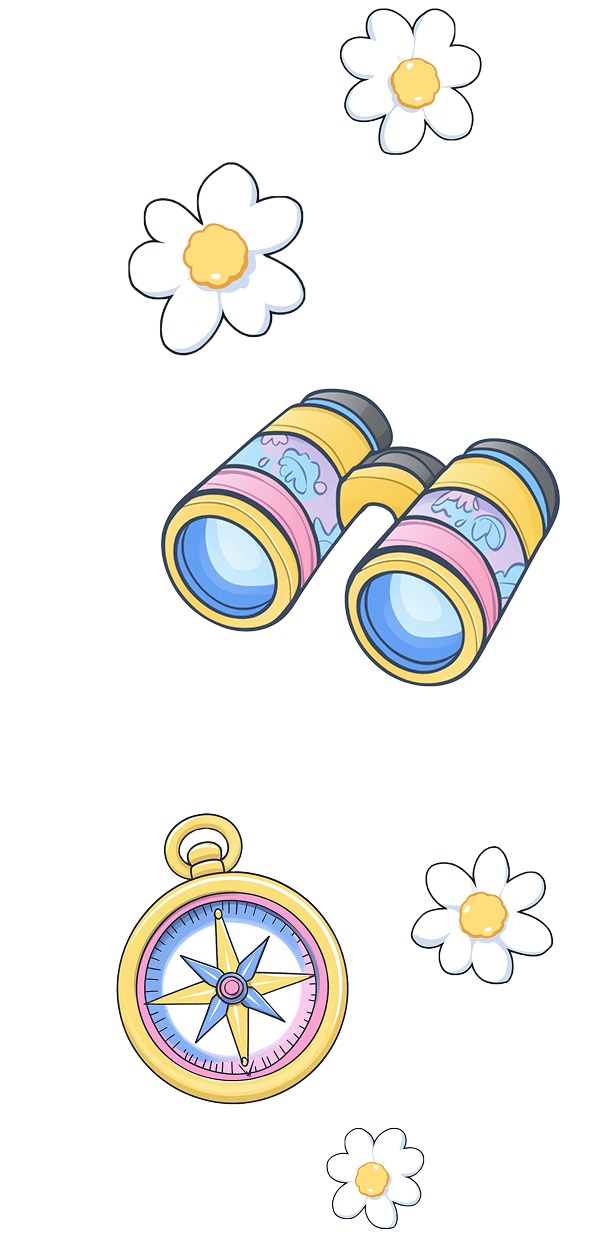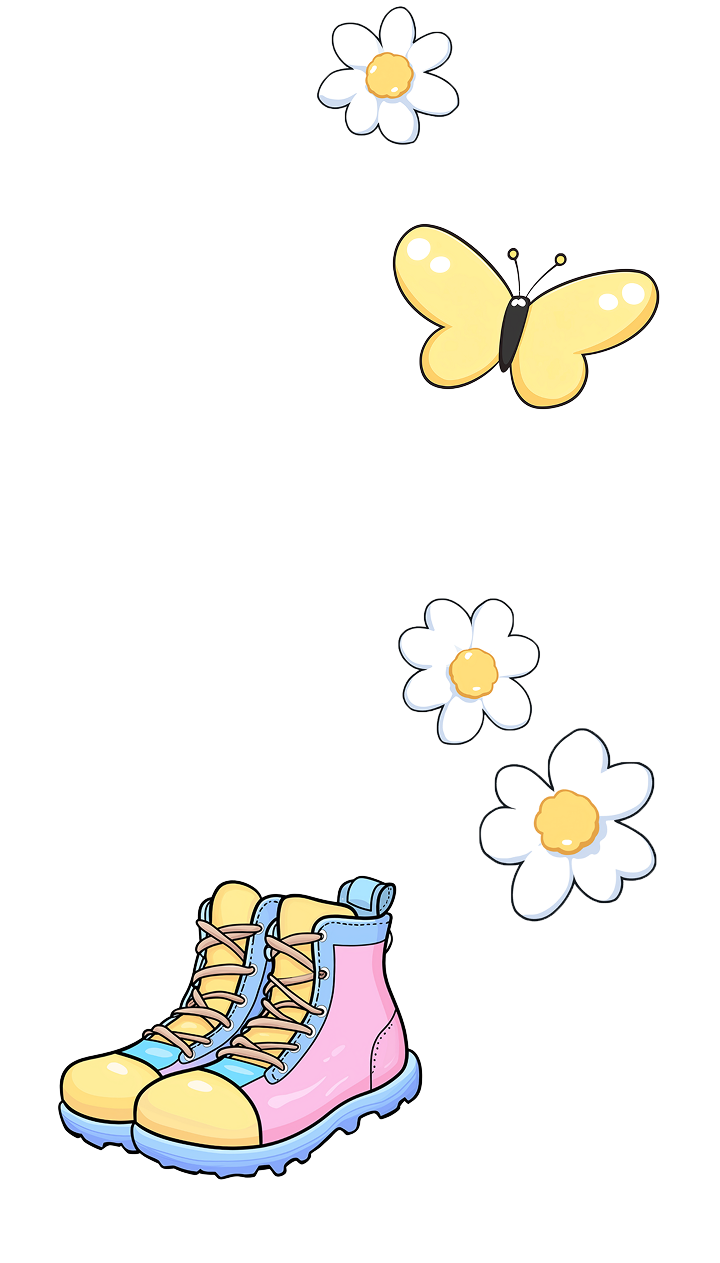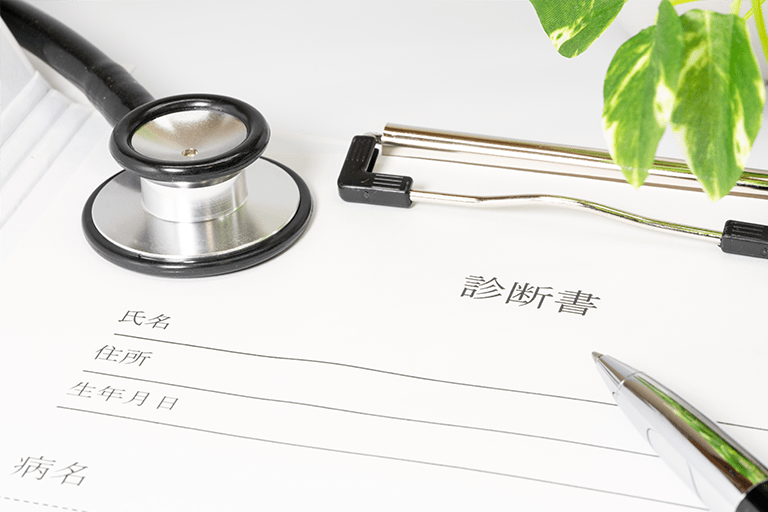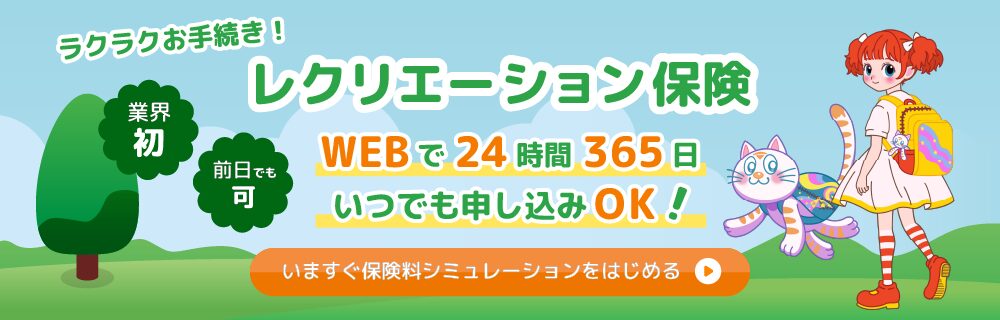スポーツ活動中にケガをした際、頼りになるのがスポーツ保険です。しかし、保険金の請求手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
特に、「診断書は必要?」「手続きの流れはどうなるの?」といった疑問は、初めて保険を請求する方にとって大きなハードルとなります。
この記事では、スポーツ保険の請求手続きについて、初心者でも分かりやすく、具体的な流れを解説します。
さらに、診断書の必要性や注意点、効率的に手続きを進めるためのポイントも詳しく紹介するのでぜひ参考にしてください。
スポーツ保険とは?
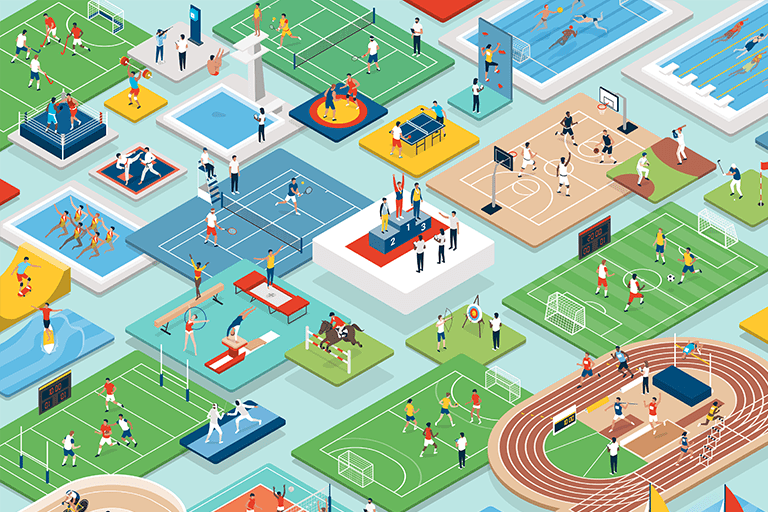
スポーツ保険とは、スポーツ活動中に発生したケガや事故に対する補償を提供する保険です。
クラブチーム、レクリエーション活動など、さまざまなシーンで加入されることが一般的です。
特に、公益財団法人スポーツ安全協会が提供する「スポーツ安全保険」は、日本国内で広く利用されており、団体活動中のケガや賠償責任をカバーします。
スポーツ保険は比較的低コストで加入できるため、スポーツをする際やボランティア活動を行う際は加入することを強くおすすめします。
スポーツ保険の主な補償内容は以下の通りです。
| 傷害保険 | ケガによる入院、通院、死亡、後遺障害に対する補償。 |
|---|---|
| 賠償責任保険 | 他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合の補償。 |
| その他の補償 | 熱中症や細菌性食中毒など、特定の事故にも対応(保険の種類による)。 |
保険金を請求するとき、診断書は必要?

結論から言うと、スポーツ保険の請求時に診断書が必要かどうかは、請求金額によって異なります。
公益財団法人スポーツ安全協会が販売する「スポーツ安全保険」を例に見ていきましょう。
請求額が30万円以下の場合
スポーツ安全保険では入通院保険金請求額の合計が30万円以下の場合、東京海上日動からの求めがない限り、原則として医師の診断書の提出は不要です。
この場合、医療機関の領収書や診察券のコピーなどで代用が可能です。
請求額が30万円を超える場合
請求額が30万円を超える場合は、原則として医師の診断書が必要となります。
診断書の取得には費用がかかりますが、これは自己負担となります。
スポーツ保険の請求手続きの流れ

スポーツ保険の請求手続きは、事故発生から保険金受け取りまでの一般的な流れを5つのステップで説明します。
なお、具体的な手続きは保険会社や保険の種類によって異なる場合があるため、請求する際は、加入しているスポーツ保険の約款や公式サイトを確認しましょう。
ステップ1:事故発生後、速やかに事故通知を行う
ケガや事故が発生したら、まず保険会社または保険代理店に事故通知を行う必要があります。
この通知は、事故発生後できるだけ早く行うことが重要です。
事故通知が遅れると場合によっては保険金が支払われないリスクも発生するため、迅速に行いましょう。
事故通知の方法は、各スポーツ保険によって様々ですが、一般的には「オンライン」「電話」「書面」の3つとなります。
また、事故通知時には、以下の情報を準備しておくとスムーズです。
- 被保険者の氏名、保険証券番号
- 事故発生日時、場所、状況
- ケガの程度や受診した医療機関の情報
ステップ2:必要書類の準備
事故通知後、保険会社から請求に必要な書類が送られてきます。
一般的な必要書類は以下の通りです。
- 保険金請求書
保険会社指定のフォーマットに必要事項を記入。 - 医療機関の領収書または診察券のコピー
治療費や受診の証明として。 - 診断書(必要に応じて)
ケガの詳細や治療内容を証明する書類。 - その他の書類
事故状況報告書や第三者からの証明書(賠償責任の場合など)。
スポーツ安全保険の場合、上述した通り、入通院保険金の請求額が30万円以下であれば、原則として診断書の提出は不要です。
代わりに、保険金請求書の「治療状況欄」に必要事項を記入し、医療機関の領収書や診察券のコピーを提出することで対応可能です。
ただし、請求額が30万円を超える場合や保険会社が治療内容の詳細確認を求めた場合、後遺障害や死亡保険金の請求の場合は診断書が必要となることがあるので、手配しておくと良いでしょう。
診断書が必要な場合、医療機関に依頼して発行してもらいますが、発行費用(一般的に2,000円〜6,000円)は自己負担となり、保険金として支払われません。
診断書を取得する前に、保険会社に必要性を確認することをおすすめします。
ステップ3:書類の提出
必要書類を揃えたら、保険会社に提出しましょう。
提出方法は、郵送、オンラインアップロード、または代理店経由など、保険会社によって異なります。書類に不備があると、差し戻しや手続きの遅延につながるため、保険会社が提供する提出書類リストや記入例を参考に、正確に準備しましょう。
また、診断書などは発行から〇ヶ月以内のものなど、期限が決められていることがあります。
期限切れの診断書を提出すると不備扱いとなる可能性があるため確認しておくことが大切です。
さらに保険金請求権には3年の時効があるため、事故発生から3年以内に手続きを完了させましょう。
ステップ4:保険会社の審査
提出された書類をもとに、保険会社が審査を行います。
この審査では事故が保険の補償対象に該当するか、提出書類に不備がないか、治療内容やケガの状況が保険の支払い条件を満たしているかなどのチェックが行われます。
審査に無事通過したら、指定した口座に保険金が振り込まれます。
追加の確認が必要な場合、保険会社から連絡がありますので、迅速に対応しましょう。
ステップ5:保険金の受け取り
審査が完了し、支払いが承認されると、指定の口座に保険金が振り込まれます。
支払い内容は、保険会社から送られる「お支払いのご案内」で確認できます。
一部の保険会社では、オンラインの契約者専用サイトで支払い状況を確認できる場合もあります。
保険金の受け取り後、領収書や書類は時効(3年)が過ぎるまで保管しておくことをおすすめします。
よくある質問

スポーツ保険の請求手続きについて、初心者が抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1:事故から時間が経ってしまった場合、保険金は請求できますか?
A1:はい、事故発生から3年以内であれば請求可能です。
ただし、時間が経つと必要書類の準備が難しくなる場合があるため、早めの対応をおすすめします。
Q2:診断書の発行費用は保険でカバーされますか?
A2:いいえ、診断書の発行費用は保険金の対象外です。
自己負担となるため、診断書が必要かどうか事前に保険会社に確認しましょう。
Q3:団体活動中のケガの場合、誰が手続きを行うのですか?
A3:通常、被保険者(ケガをした本人またはその保護者)が手続きを行います。
ただし、団体活動の場合は、主催者や管理者を通じて事故通知を行う必要がある場合があります。
Q4:保険金の支払いまでどのくらいかかりますか?
A4:書類が完備していれば、通常5営業日以内に支払われます。ただし、書類に不備がある場合や追加確認が必要な場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
スムーズな請求のためのチェックリスト
最後に、保険金請求をスムーズに進めるためのチェックリストを紹介します。
事故が発生した際はぜひ参考にしてください。
- 事故発生後、速やかに保険会社に事故通知を行う。
- 事故発生日時、場所、状況を記録し、保存する。
- 保険会社から送られてきた書類を確認し、必要書類を揃える。
- 診断書が必要な場合、保険会社指定のフォーマットを確認し、医療機関に依頼。
- 書類提出前に、記入漏れや誤りがないかダブルチェック。
- 診断書を受け取ったら、内容に誤りがないか確認。
- 書類提出後、保険会社からの連絡に迅速に対応。
- 保険金受け取り後、書類を時効(3年)まで保管しておく。
まとめ:大きな事故でなければ診断書は基本的に不要

スポーツ保険の請求手続きは、事故発生後の迅速な対応と、必要書類の正確な提出が重要です。
診断書の提出が必要かどうかは請求金額によって異なりますので、事前に確認し、適切な手続きを行いましょう。
また、事故通知や保険金請求には期限がありますので、速やかな対応を心がけてください。
スポーツ活動を安心して楽しむためにも、万が一の際の手続きについて理解を深めておくことが大切です。本記事が、皆様の参考になれば幸いです。